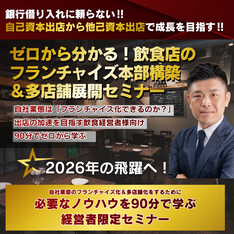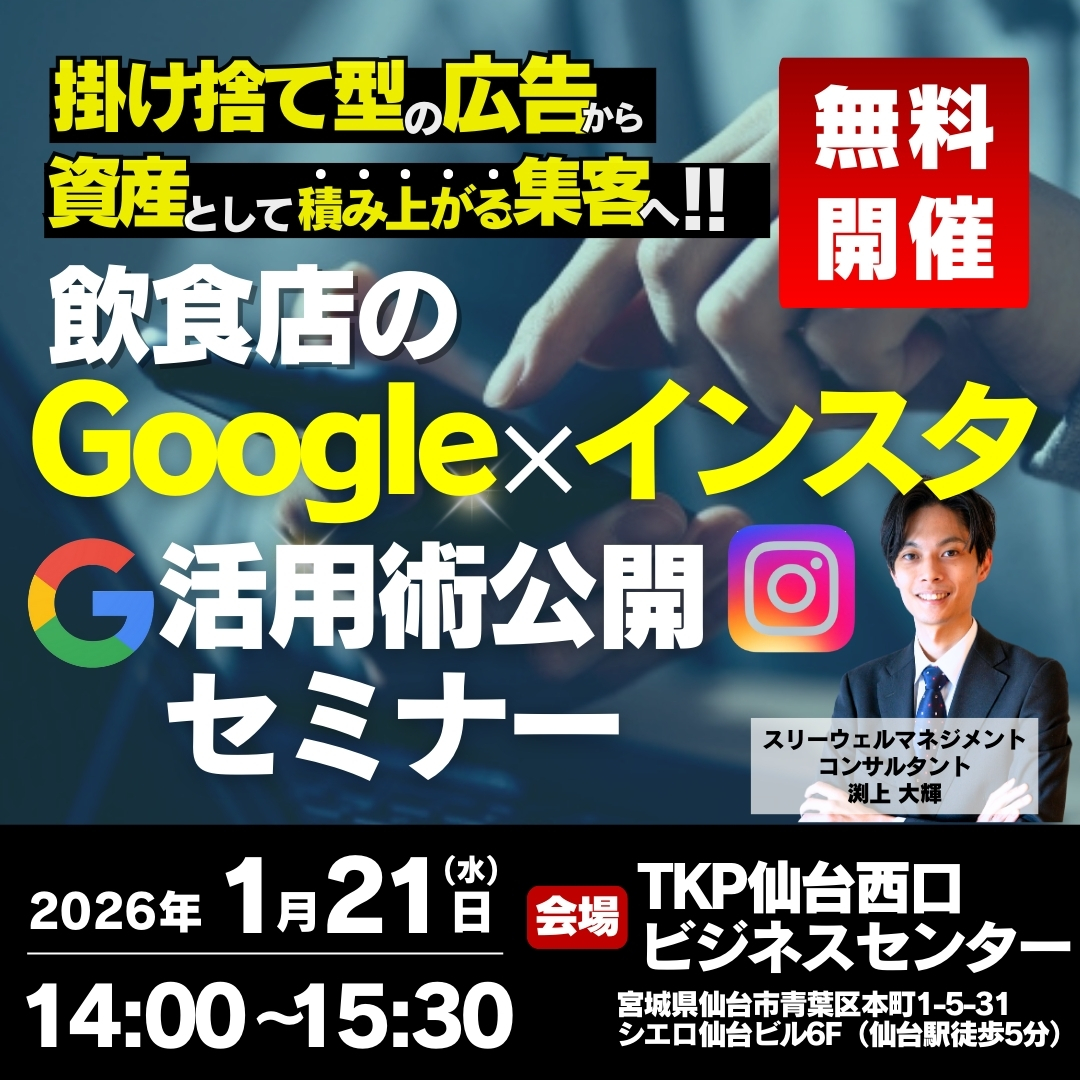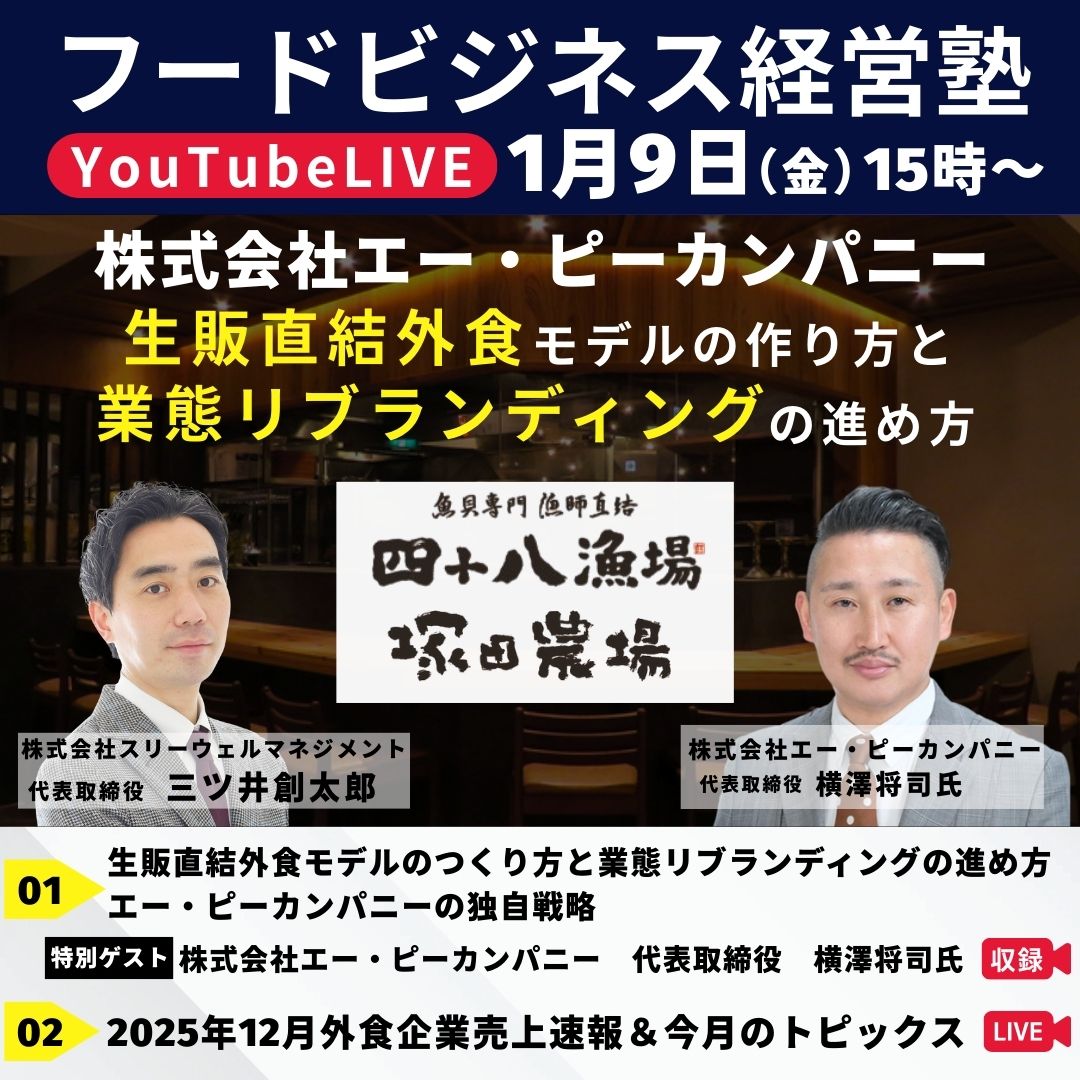お話を聞いた株式会社Goodmarket&shops 代表取締役 清水 暁弘さん
【これまでのGoodmarket&shopsと清水 暁弘さんの記事】
◾️Goodmarket&shops
11月12日、馬肉と吉田のうどんを二毛作で提供する「大衆馬肉酒場 冨士山(ふじやま)」が水道橋にオープン(2014.11.12)
古民家復興プロジェクト発足!7店舗が集結した複合型飲食店 『ほぼ新宿のれん街』、3月17日に代々木にオープン(2017.03.16)
スパイスワークス下遠野氏とGood market & shops清水氏による「歌舞伎町レッドのれん街」が、新宿センター街の横町「思い出の抜け道」内に9月15日オープン!(2019.09.10)
「ほぼ新宿のれん街」に「ニューキッチンイロハ」が開業。昭和レトロとピッツェリアを融合した“ツマンデ吞めるピザパーラー”。ディナーからランチ、カフェ利用まで1日を通して集客(2021.05.21)
「ほぼ新宿のれん街」に「倉庫別館」がオープン!個性豊かな7店舗が新たに倉庫内に集結。今後、空き倉庫を活用した“倉庫型横丁”の展開を視野に入れたモデルケースに(2022.01.28)
◾️清水 暁弘さん
【NEXT イノベーターズ】FILE.3 第5世代のトップ対談!二人の35歳の経営者が飲食の未来を描く
大山:こんな感じで(上記)清水さんのことは、ずっとつぶさに取材させていただいてるんですけど、清水さんといえば横丁の仕掛け人ということですが今現在、様々手掛けていると思いますけども、何か新しく仕掛け始めたことっていうのはありますか?
清水さん:実は昨年の 8 月、ちょうど1年ほど前に私の地元の静岡県西部の浜名湖にある 100 年続いた清風荘という民宿 7 棟(土地総面積 5171.34 ㎡/1564.31 坪)の事業承継を受けました。まずその1棟をリノベーションし、一棟貸しホテルを開業しました。「浜名湖 清風荘 seifuso」という宿泊施設になります。
…と、聞いていたので、実際に泊まってきました!


以下、実際に浜名湖 清風荘に宿泊体験をしたあと、という前提でお読みください。
▼
大山:今回の清風荘ですが、どのような経緯でプロジェクトを始めることになったんですか?
清水さん:これからの食に対しても様々な引き出しを持っておかなくてはいけないなという想いと、地方のグッドロケーションな場所に何かしらを出したいという想いは昔からありました。そんな中、不動産を見るために様々な場所をドライブしながら周った際に偶然清風荘の隣の土地が空いているのを発見し、そのついでに清風荘を覗いたところそのロケーションに一目惚れしました。

大山:どうして浜名湖だったんですか?
清水さん:浜名湖のある静岡県西部は私の地元です。静岡の観光地といえば、熱海、伊豆、富士山・・・県内の東部の方に大体位置しており、西部エリアは観光地と呼ばれるものがほとんどありませんでした。ただ、浜名湖は日本最大の海水と淡水が混ざる汽水湖であり水産資源が800種類あると言われております。
また釣りやサーフィン、近くにゴルフ場もありアクティビティも豊富なエリアなのです。その浜名湖の魅力を伝えるべくこの場所を選びました。


大山:なるほど。今回の清風荘再生プロジェクトのコンセプトをお聞かせください。
清水さん:まず「ぼやけた浜名湖の魅力を鮮明にする」というコンセプトを掲げました。ロケーションを最大限に生かすこと、浜名湖の水産資源を最大に生かすこと、既存の清風荘の温かみを残すことを掲げプロジェクトがスタートしました。
大山:しかし、すごい規模ですね。
清水さん:はい、全部で7棟(体育館付)で土地総面積 5171.34 ㎡(1564.31 坪)あります。まさに宿街を作るイメージで考えています。ただ、もちろん予算もあるので、まずは一番ロケーションの良い2号館から着手しました。今後は、ひとつずつ時間をかけて増やしていければなと思います。

大山:なるほど。2号館の内装やコンセプトについて、インバウンドを意識されたのでしょうか?
清水さん:先程も申し上げたように、浜名湖はうなぎ、牡蠣、シラスなどの水産資源が800種類以上あります。そこから逆算した時に、ここが我々の飲食の原点につながることでもあるのですが、この水産資源を食べてもらう事をメインにしないといけないと思い、ではなにが一番いいかと考えた結果、日本の昔ながらの風景らしく土間、囲炉裏や炉端に辿り着きました。
土間ありきで全て設計をやったのでそういう意味では結果的にインバウンドにつながる可能性はありますが、最初の思いとしては、浜名湖の魅力を伝えるため、浜名湖の生産資源といったところから、囲炉裏と土間に行きついて、あのような内装になりました。


大山:外国の方にも絶対にウケるような感じがしますよね。
清水さん:浜名湖はまだどこか知らない方が多いと思うので、どこかで火がつけば来ていただけるのでしょうが、まだまだ時間はかかるのかなと思っています。
大山:少し話は戻りますが、事業承継までの経緯をお聞かせください。
清水さん:清風荘の隣地の募集を見て、不動産屋を通じて前オーナーさんに直談判しにいきました。前オーナーさんは当初は事業承継をするつもりはなかったようですが、約 1 年で何度か足を運び我々の想いを伝えさせていただき承継させていただくことになりました。
大山:それはまさに、以前お聞きしたように代々木ののれん街を造られた時と同じような感じですね?
清水さん:はい、代々木も 1 軒の物件から始まって、家主さんへ我々の想いやビジョンを共感していただき、ご理解いただきプロジェクトを進めることができました。
大山:やっぱりそういう時は、熱量を伝えていくような作業になるんですか?
清水さん:熱量もそうですが、誠実さと必ずやり遂げるという部分を伝えていくこと、共感していただくことですね。
大山:まだ敷地の中に、前オーナーさんが住まわれていると聞きました。
清水さん:はい。やはり住み慣れた所から引っ越したくないだろうと思ったので、もしそうであれば敷地内に小さいものを建てませんか等、いろいろなことを提案しようと考えていました。我々が事業承継したあとも、前オーナーさんには住んでいた元々の敷地内の自宅にそのまま住んでいただいています。
大山:清風荘を訪れて、最初に思い浮かべたのがもう宿だったんですか?それともレストランにしようとか。
清水さん:清風荘というのは、1号館から6号館までとプラス体育館があるのでいろいろな構想をしました。
宿であったり、敷地内にカフェもできるでしょうし、最終的には一帯が宿泊施設含めた宿街というか、一つの街みたいな形になればいいなっていうのは最初に見た時に湧きました。
大山:敷地も大きいし、レストラン一つを作るよりは、その建物の形も生かしながら宿にしていこうというわけですね?
清水さん:そうですね。これは間違いなくコロナ禍という状況でもあり一棟貸しであれば、プライバシーとソーシャルディスタンスが一定数保てるので。
大山:逆に言うと、大手さんとの差別化という意味もありますよね。
清水さん:それもあります。大手さんであれば資本力があるので大規模な開発ができますからね。大手さんであればスクラップアンドビルドして新しい建物を建設していたと思います。
ただ我々のような中小企業はそんなに資本力もないですし、100 年続いた清風荘という宿を今後も残していきたいという想いがありこのような形になりました。

大山:実際に僕は行かせていただいて、ところどころ清風荘の名前も残ってますし、躯体も残ってる。「あぁ清水さんらしいな・と思いました(笑)。デザインとか作りのこだわりといったところもちょっと聞きたいです。
清水さん:もともと私は不動産のスクラップアンドビルドというものに対して、学生時代からすごく違和感を持っていて、日本の不動産の特徴は『壊しては新しいものを作る』というようなことが昔から行われているわけですが、残す文化というか、不動産としての在り方として古いものに価値を与える。
あとは建築として、清風荘というものを活かしながらやってほしいという、設計側へのリクエストを出させていただいたんです。その設計やディレクション、運営も私の同級生の仲間で作り上げました。僕の好みも分かっている人たちなので、ああいう形になったというか。みんなで改装前の清風荘に泊まりながら意見を出し合ってプランを練りました。



大山:実際にどんな方々と作ったんですか?
清水さん:僕の友人が河口湖の方で Y l&Co Hotel という一棟貸しのフラッグシップ的な宿と sinso という布団メーカーを運営していて、彼にディレクションを依頼しました。また、設計やロゴも共通の同級生と一緒に作り上げました。
運営はもちろん私の高校の同級生の戸塚庸平率いる Stove’s market が運営しています。戸塚はかつてホテルニューオータニで最年少でキャプテンというポジションを任されていました。Stove’s market 立ち上げ15年目でホテルの運営をお願いできたこともうれしく思います。


「清風荘」の名を残しつつリゾート感を醸し出す、まさに清水さんらしいリノベーション。窓枠のサッシも以前の清風荘のまま。
大山:実際に私たちも行かせていただいて素晴らしいなと思ったんですけど、もし今後外国人が来て火がついた場合泊まれなくなってしまう可能性あると思うんですが、敷地を広げていくことも考えているんですよね?
清水さん:隣の1号館を来年に着手しようかなと思っています。

大山:1号館も一棟貸しでやられる感じですか?
清水さん:そうです。1号館の方は面積が少し小さく2号館の7掛けぐらいなので、少しコンパクトになりますが、今の面影を残しながらやろうと思っているので、少しリーズナブルにできるかなと思っています。
大山:構想を聞かせていただいて、向かい側のマリーナも視察させてもらいましたが、あちらは別の大家さんが持ってたんですか?
清水さん:2号館を着手して工事中に、たまたま清風荘を仲介してくれた不動産屋が沿いにある小さなマリーナがあると紹介してくださり、それを見に行ったんです。
清風荘に来たお客さんが駅からマリーナについて船に乗って清風荘に来てチェックインするというのも面白いなとか、釣りを楽しんでいただいて自ら釣ったものを炉端で焼いたりとか刺身で食べられるというオプションは最初から考えていたので、自分たちのマリーナができるなら、こんなにいい事はないなと。それで僕が買わないといけないなと思い(笑)、その場で即決購入しました。桟橋といいうのは特別な権利で簡単に発行できるものじゃないので、その権利自体がかなり貴重です。

大山:実現したら面白いですよね。今後、清風荘、浜名湖プロジェクトの完成体っていうのは、どんなふうに考えていますか?
清水さん:どこを完成とするかっていうところではあるんですけど、浜名湖や南部の方の魅力が浸透してくれればいいなと。

大山:ちょうど、距離的にも東京〜大阪の間でしたね。ちょうど時間的にも。途中下車してもらうというようなところで考えても、ベストな場所ですよね。
清水さん:距離はあると思うのですが、今はありがたい事に予約を見ると、千葉、滋賀、京都・・・日本のいろんなところから来ていただいていております。その方々は、おそらく浜名湖をピックアップして来てくれてると思うんですよね。
とはいえ、JR の駅(新居町駅)からタクシーで5分と、そんなに距離があるところではないので。車で来られる方もいますが、電車でも比較的来やすいかなと思います。
大山:利用客の層は、どんな方が多いですか?
清水さん:ご家族の方もいらっしゃいますが、オフサイトミーティングのオファー、企業研修とかもあります。
大山:元々合宿場ですし、大人数には向いているわけですね。
清水さん:全国展開している企業さんも、ちょうど浜名湖が合間のロケーションというところで来やすいのかなと思います。

大山:いいですね!この清風荘に限らず、なんかこういう絶対立地みたいなものがあれば、またやってみたいみたいな野望はありますか?
清水さん:もうすでに千葉の市原の鶴舞という地域の築 140 年の古民家を買わせていただいて、これから着手します。
そこはリノベーションしてゴルファー向けの民泊みたいな感じでやりたいと思っています。ただやはり今我々の使命としては、浜名湖でやらなきゃいけないことが沢山あって、カフェも作りたいですし、マリーナも綺麗にして、そこも泊まれるようにしたいですし、体育館でウェディングをしてもらったり…、いろいろな構想はあります。

以前の清風荘
大山:まさに清水さんたちにとっては「大人の遊び場」みたいな感じですね(笑)。
清水さん:我々のホームページの最初にも載せている「食から始まる街がある。」っていうのを掲げていて、代々木もそうなんですけど、浜名湖もその定義に則って飲食、食、生産資源から広まるような街づくりという風になっていったらいいなと思いますね。
大山:グループ全体として、今後の展望的な部分はどんな感じで考えているんですか?
清水さん:私も年を取りますし、スタッフも年を取っていくのでバックボーンの情勢が変わってくると思うんですよね。
例えば地方に行ったり、地元に戻りたいとか、独立したり、個人個人の様相が変わってくるところで、それに対応できるようなことを多角的に、我々としてもこの飲食という枠の範囲内で色んなマーケットにチャレンジしていきたいと考えています。
大山:具体的なところでは、独立支援みたいな制度はあったりしますか?
清水さん:あります。運営会社が10社あり、独立している子もいます。例えばストーブスの幹部の子が今後、地方で独立します。独立支援は我々が不動産を取得してお店を作り、そこを業務委託というような形にして最初の資金とかも少しつけてあげて、というイメージです。
あとは「牛タン いろ葉」「うな串 焼鳥う福」は FC パッケージがありますのでまずはFCとして始めて、お金を貯めて自社業態を始めるという仲間もいますね。
大山:数値的な目標っていうのは、定めていたりするんでしょうか?
清水さん:創業時から数値的な目標は全く定めてないですね。もちろんなんとなく僕の中のイメージで、このぐらいにしたいな、このぐらいまでにこうなってたいなっていうのはあるのですが、飲食店っていうのは物件ありきなので、そこをコミットしすぎて変な物件を契約してしまうというのが怖いので。
もちろん、ざっくりとした目標は掲げますが、そこに是が非でもコミットするぞっていう目標はないですね。
大山:それでは、今後の中長期の目標を言葉で言うとどういうふうになりますか?
清水さん:いろんな都市、いろんな方々と一緒に事業をやっていきたいなっていうのが根底にあるところと、僕はまだまだ日本は捨てたもんじゃないなと思っているので、そこを深掘りしながら、新しいマーケットを開拓していきたいです。
さっきの話に戻るのですが、田舎だから何ができるとか、都心じゃないとできないとか、そういった壁をなるべくなくして、いろんな取り組みにチャレンジしていきたいですね。
大山:素晴らしいですね!これからも応援させていただきます。ありがとうございました!
編集後記
今回はまさに「清水さん、今何やってる(仕掛けている)のかな?」と思い、アクションしたところから、まさかこれほど壮大な計画に着手しているとは思いもよりませんでした(笑)。これまで横丁の仕掛け人として街に灯をともしてきた清水さんですが、これからは日本の地方都市の可能性について仲間たちと挑戦していくという新たなミッションに目を輝かせていました。清水さんと同社のこれからに引き続き注目していきたいと思います。(聞き手:大山 正)
◾️こちらの企業・商品に興味・関心、見学希望等、連絡を取りたい方は下記フォームよりお問い合わせください。弊社が中継し、ご連絡させていただきます。(メディア取材、各種コラボレーション等)