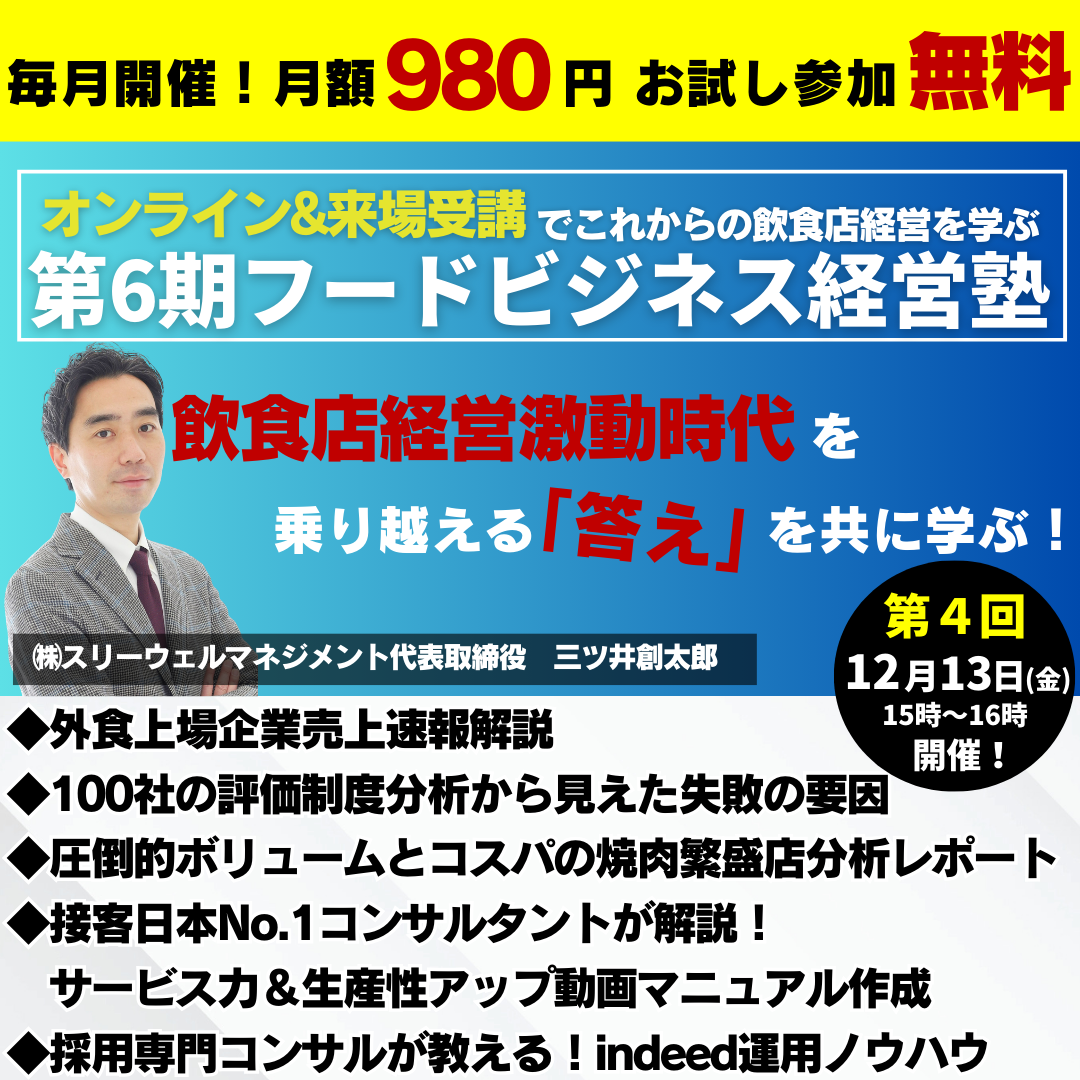残りの半分をスーパードライで奪取せよ!
『個性の塊だ』
アサヒビール市場開発本部外食営業第二部の示村隼は、直感的に思う。2013年秋、市場開発本部に異動になった直後、示村は初めてその社長に会う。
1984年生まれの示村よりも、社長は7歳年上。30代の若さながら、40店舗近くを展開する外食企業を経営している。当然ながら、カリスマ性は高い。
この外食が扱うビールの半分はスーパードライ、残りは競合他社製。
示村のミッションは、この外食が扱うすべてのビールを、スーパードライに切り替えることだった。
前任者と一緒に挨拶に訪れて、そのまま会食へ。示村は目の前の社長を必死に観察する。特に、人柄を。「ビールを全部、うちにしてください」などとは、口が裂けても言葉にはできない。「ハイ」を重ねて、笑顔を返すだけである。
「最も重要なのは、お客様との人間関係が築けているかどうかです。提案一つにしても、響き方はまるで違うものになる」
と、示村は話す。
初回の面談は、人間関係をつくるための第一歩である。人間関係をつくるに当たり、社長に対する自分の立ち位置をどうするか。7歳年上の社長は示村にとっては“アニキ”のようなもの。社長の立場で考えるなら、示村は“一番下の弟”に当たるだろう。
『基本として、このポジショニングで臨もう…』。こう示村は考えた。
「オーイ、行くぞ!」と社長が言えば、「ハイ」と示村は即座に答えていく。
なぜアサヒは復活できたのか
アサヒは、1987年発売の「スーパードライ」の大ヒットにより飛躍した会社だ。それ以前は、深刻な経営危機に直面していた。
ドライ発売の87年とは、バブルの始まりに当たる。資金調達は容易になっていく。
しかも、当時のアサヒ社長は、旧住友銀行(現在の三井住友銀行)副頭取から転じた樋口廣太郎(故人)。投資に対する逡巡はなかった。
設備投資は、樋口が86年に社長着任する以前は、10年間で40億円程度だった。これが、八六年から茨城工場がほぼ完成する90年(同工場の竣工は91年4月)までの5年間で、総設備投資額は約4183億円に及んだ。これにより、生産能力は86年に比べて91年には5倍に拡大。スーパードライの旺盛な需要に応える生産体制を整備する。
広告宣伝費も年間100億円未満だったのを、樋口は「こんなことでは売れるものも売れない」と、ドライの発売以降は年250億円前後に引き上げたとされる。
最悪の85年におけるアサヒの販売量は3505万箱(1箱は大瓶20本)。これが90年に1億2273万箱、91年1億2887万箱へと拡大する。同じくシェア(販売)は85年9.6%、86年10.1%、ドライ発売の87年12.7%、88年20.1%、90年23.9%と上昇。アサヒは経営危機から見事に脱する。
ちなみに、なぜスーパードライが戦後を代表するヒット商品かといえば、単純に「売れたから」という理由だけではない。ドライビールというジャンルを市場に定着させた上、86年には3億8865万箱だったビール市場そのものを、最盛期の94年には出荷ベースで5億7300万箱(発泡酒含む)へと、ほぼ1.5倍に拡大させたのだ。アサヒのシェアはその後、首位になった01年が38.7%、03年が39.9%で最大に、2014年は38.2%だった。
一方、14年のビール類(ビール、発泡酒、第3のビール)の市場規模(総出荷量)は、前年比1.5%減の4億2707万。10年連続のマイナスであり、94年と比べるとほぼ四分の三の水準だ。しかし、ドライ発売前の86年よりもまだ大きい。
アサヒの復活劇は、美しい話ばかりではない。90年にバブルが崩壊し、ほぼ10年にわたりアサヒは財務の建て直しで苦しむことになる。バブルに踊った“ツケ”が回った結果だった。
それはともかく、設備やCMはお金でどうにでもできる。どうにもならないのは、やはり人である。87年から現在まで、ライバル3社との熾烈な戦いを繰り返している。特に90年代には、財務面に不安を抱えながらもシェアを伸ばしていく。戦線が拡大した分、営業マンは必要となる。
“即戦力”となる営業の人材を、アサヒは90年代に中途採用に求めた。
どうすれば社員を定着できるのか
「人をとれれば、事業をもっと発展できるのに」
こう考えている外食会社のオーナー経営者はいるのではないか。
アサヒも同じだったのだ。
採用以上にポイントとなるのは、中途で入った人をいかに戦力として生かすである。
アサヒの特徴は、社員の離職率が低いこと。ビール会社の特性上、数値目標に追われる営業職が多いのにだ。なぜか。
この点は、第1回で記したが「(アサヒは)仲間意識が高い」(示村)のは背景だろう。現実に、中途入社して支店長をはじめ幹部に出世し若手育成に手腕を発揮した人はいる。また、勤務先の大手証券会社が破綻してしまい、転職してエース級の営業マンとして活躍中の人もいる。
では、具体的にどうしているのか。
示村は「毎月一回、営業をとめて部で会議をもちます。進捗状況をはじめ、抱えている問題点、成功事例などを営業マン個人としてではなく、部として共有するのです。つまりは“知の共有”です」と語る。
アサヒは、スター選手をつくらない。逆に、どうやら“落ちこぼれ”もつくらない。一般に、どんな組織も「2・6・2の法則」があるといわれる。トップの2は優秀、6は普通、最後の2はパフォーマンスが劣る、という構成になりやすいというもの。成長性が高い新興企業ではボトルの2は会社を去り、離職率を引き上げる。一方で、成熟した伝統企業では、ボトルの2は会社に居座り内部から組織を衰退させていく。
アサヒは、ボトムの2を消しているのではないか。部の横断的な会議を開くなど、政策的にである。チーム内で互いに助け合う仕組みを築き、個人を孤立させない。
ラグビーの精神性である、「One For All、All For One(1人はみんなのために、みんなは1人のために)」に通じる考え方が、企業文化として存在しているようにも思える。
チームとして一人を支えるこのやり方は、人によっては一人前に成長するのに時間を要する。だが、知の共有と、仲間意識の強さとで、アサヒはこれを選択している。80年代の経営危機の時代から、アサヒは取引先に対しても、その多寡とは関係なしに『お客様はみな同じ』といった平等の精神があったが、これが社員に対しても働いているのかもしれない。社歴や出身校、新卒と中途の別などは関係なしに、社員は仲間であり与えられる機会は平等といった形で。
示村は、“個性の塊”のような社長へのアプローチを繰り返す。知を共有する上司とともに、社長との会食も重ねる。
「社員の接客力を上げたいんだよね」
社長は本音を、弟分の示村に漏らし始めた。
最終回に続く