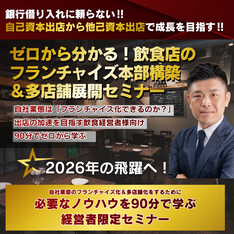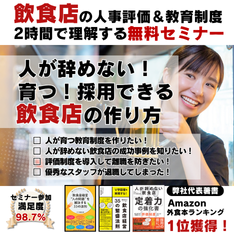神田・赤坂で大繁盛店となった「東京オーブン」を運営する、株式会社テンプルボーイの創業者の渡邉真祐さん
大山:改めまして、自己紹介をお願いします。
渡邉さん:2010年に神田でカフェを開いたのが、私の飲食人生の始まりでした。以来13年間、生産者の想いを届けるレストラン「東京オーブン」を中心に、飲食店経営に没頭してきました。
そして2023年3月、会社ごと事業を譲渡し、翌月からはイシン株式会社というメディア企業で、ビジネスパーソンとしての新たな道を歩んでいます。経営者から会社員へ、まったく異なる世界への転身ではありますが、今は毎日が学びと成長の連続で、非常に充実しています。
大山:現在は志新たにお仕事をされているということですね。「東京オーブン」という繁盛店をやられていたかわけですが、現職中の会社の状況はどのような状態で、何を目指していたのですか?
渡邉さん:そうですね、この東京オーブンですが、“生産者の想いを届ける”というコンセプトを掲げた店でした。単に食材の品質や鮮度を打ち出すだけではなく、その背景にある日本全国の生産者の情熱・想いを伝えることが、私のミッションだったんです。
たとえば、三陸・越喜来湾の漁師、遠藤さんのムール貝。彼は元々ホタテ漁師でしたが、情熱を持ってムール貝の養殖に人生をかけている。そんな生産者を、料理という形で世の中に紹介したかった。「三陸産のムール貝です」ではなくて「遠藤さんの育てムール貝です」を消費者にメッセージとして届けたい。そんな想いを込めて「生産者の顔が見えるレストラン」として展開していました。

大山:最初、東京オーブンをオープンしてどのような感じでしたか?
渡邉さん:オープン当初は正直、想像以上に苦戦しました。立地的な難しさもあり、ほとんどお客様が入らない日々が続きましたが、それでも“伝えたい想い”があったので、諦める気持ちは一切なかったんです。
地道に営業を重ねていく中で、南部鉄器を使ったオーブン料理がメディアに取り上げられるようになり、徐々に注目が集まり始めました。メディアの取材が続き、TBSの「王様のブランチ」でローストチキンが紹介され、大きな転機が訪れました。苦労した分、手応えも喜びも大きかったですね。
大山:そうでしたね。その後、2号店を出していくのですよね。
渡邉さん:はい、本店が満席になるようになり、徒歩1分の場所に2号店「東京オーブンプチ」を開きました。そこからは、全国の生産者を訪ね歩く日々が始まりました。畑で農作業を手伝ったり、宮崎や北海道へ足を運んだり。現場で汗を流すことで、さらに深く生産者の“想い”を理解でき、それがレストランの表現にも深みを与えてくれました。

大山:当時、フードスタジアム主催のセミナーにも出ていただいていましたよね。
渡邉さん:はい、登壇させていただきました。「六次産業化とミッション経営」をテーマにしたセミナーで、今も記憶に残っています。基調講演をされたのがエーピーカンパニーの米山さんで、控室で初めてご挨拶したときのやり取りが、今でも自分の中の指針になっているんです。
僕が「生産者を応援するレストランを広げたい」と熱く語ったら、米山さんが一言「その規模感なら、まずは年商20億円が必要だね」と。あの瞬間、ただ想いを語るだけでは社会にインパクトを与えられないという現実に気づかされました。
あの一言は、店舗展開を進めるきっかけにもなり、自分の目指す道をより明確にしてくれました。結果として、飲食業から離れた今でも、そのときに植えられた“志を形にする力”という学びは、自分の中に深く根付いています。
大山:赤坂店は、ホテルの1Fのレストランでコンペが通っての出店でしたよね。
渡邉さん:ホテルの一階という環境は、飲食店にとって簡単ではありませんでした。特に朝食営業という未知の領域には、戸惑いも多かったです。最初は本当に泣きそうになりながら運営していました。でも、だからこそ発見もあった。例えば外国人スタッフの雇用がしやすいことや、朝食営業を条件にした物件は競争率が低く、戦略次第で大きな武器になるということ。飲食店としての新しい可能性を見出せたのは、大きな財産でした。
しかし「この戦略でいける」というタイミングでコロナが来てしまいました。

大山:そうでしたね。そこからコロナ渦に入っていくわけでえすが、会社はその後どんな状況で、どんなことをやられていたのですか?
渡邉さん:コロナ直前に、2軒目のホテルレストランの朝食運営をスタートしていました。場所柄、朝食以外の営業が難しかったため「この空間を有効に活かせないか」と考え、当時海外で話題になっていたゴーストレストランに目をつけたんです。ちょうど日本でもUber Eatsが上陸しはじめた時期で、「これは試すしかない」と。デリバリーに適した立地ということもあり、すぐに動きました。
そこからコロナが本格化して、通常営業が難しくなりましたが、デリバリーはむしろ活況で、神田・赤坂の両エリアで展開を広げていきました。特に東京オーブン・プチをデリバリー拠点に切り替えたのは、柔軟に動いたからこその判断だったと思います。
一方で、オフィス街の特性から来店客は激減し、夜営業を中心にしていた店ほどダメージが大きかった。お酒を出すだけで世間の目が厳しくなるような時期でもありましたし、「誰も悪くないのに、店を開けることができない」という状況に、もどかしさを感じていました。
それでも、ノンアル営業、非接触店舗、テイクアウト専門業態など、あらゆる手段を試して“生き抜く”道を探し続けました。苦しかったけれど、経営者としての柔軟さや現場力を磨く時間でもありましたね。
大山:オフィス街は本当に大変でしたよね。人が本当にいなくなってしまって。
渡邉さん:本当にそうでした。オフィスワーカーの方々がメインのお客様だったので、街に人がいないというだけで、店の存在意義が根底から揺らぐような感覚がありました。「外で飲んでるのを見られたら会社でどう言われるか」みたいな空気もあって、常連のお客様すら姿を消した。あのときの静けさと不安は今でも忘れられません。
デリバリー業態やテイクアウト業態などにも挑戦し、アフターコロナの環境に適応した飲食業の在り方を探しましたが、結果として私の場合は、店舗を縮小するという判断をしました。
大山:なかなか大変な決断でしたよね。
渡邉さん:はい、本当に大きな決断でした。コロナ禍が長引く中であらゆる手を尽くして営業を続けてきた中で、店舗を減らし、仲間とも別れなければならない局面が来たとき、「これは自分が本当にやりたかったことなのか」と自問するようになりました。
ただ、生産者を支援するという理想に立ち返ったとき、現状の延長線上にその実現がないと気づいたんです。一度立ち止まり、方向転換することもまた、前に進む選択なんだと決め、「友人経営者に会社を譲渡する」と、腹を括りました。
大山:そこからどのような転機があって、会社を譲渡していくことになるのですか?
渡邉さん:転機になったのは、赤坂で同じように飲食店を経営していたトレジオンの吉田くんの存在でした。彼もまた、三陸を応援するレストランを展開していて、業態は違えど「地域や生産者に貢献したい」という想いのベクトルが、僕とすごく近かったんです。
コロナ禍でみんなが慎重になるなか、吉田くんは真逆の選択をしていて、借り入れを使って岩手に出店したり、500万円のコーヒー焙煎機を購入したり。最初は正直「無謀すぎる」と思いました。でも、彼の目はずっと輝いていた。自分が「守る」ことばかり考えていたときに、彼は「夢をかける」姿勢を貫いていたんです。その対比に、ハッとさせられました。
経営って、9割が右を選ぶ中で、あえて左を選び突き進む力が必要なんじゃないか。そう思ったときに、「彼にだったら自分の会社を託せるかもしれない」と感じるようになりました。飲食業を手放す決断は簡単ではありませんでしたが、理念を共有できる仲間に継いでもらうことができたのは、本当に幸運だったと思っています。
大山:そうだったのですね。それで実際にどのように売却は決まったのですか?
渡邉さん:当時「自分の想いを、誰に託せるだろう?」とずっと考えていました。「志を同じくし、想いを持った人は誰かいるか?」その中で、共にレストラン業をやってきた吉田くんなら、スタッフも大事にしてくれて、東京オーブンの理念も守ってくれる——そう確信が持てた瞬間がありました。条件はふたつ。「社員を辞めさせないこと」「東京オーブンの想いをできる限り続けてくれること」。この約束を交わして、譲渡を決めたんです。2022年の終わりのことでした。
大山:そうだったのですね。ただ、M&Aを当事者間でやるというのはいろいろ大変だったのではないですか?
渡邉さん:それはもう、苦労の連続でした(笑)。2022年9月から話し始めて、「これってどうやるの?」からスタートですよ。デューデリも何も、2人で公証役場に行って、手続きを進めて…今思えば本当に手作りのM&A。でも、会社の未来を誰に託すかという本質に立ち返れば、形式にこだわるより、大事なことを真剣に語り合うことが何よりも重要だったのかなと今では思います。
大山:スタッフの皆さんにはいつどのような感じでお伝えしたのですか?
渡邉さん:年末に決断をして、年が明けて落ち着いたタイミングで、社員に伝えました。正直、驚かれましたけどね。でも、「社員を誰一人辞めさせない」という約束を守ってくれることも伝えたので、最終的には理解してくれました。結果として、今でも一人も辞めていない。僕にとって、それが何よりうれしいことでした。

定期的に訪れる援農の生産者と東京オーブンで働く仲間たち
大山:それは良かったですね。そのときは、次何しよう、どういうふうにやっていこうというのは全く決まっていなかったのですか?
渡邉さん:いえ、実はもう決めていたんです。学生時代に一緒にベンチャーをやっていた盟友・明石が代表を務めるイシンという会社がありまして。ちょうどその会社が上場を控えている中で、「渡邉、お前の“地域を応援したい”という想いは、うちの会社でも実現できるんじゃないか?」と声をかけてくれたんです。飲食という現場からは離れるけど、より大きなスケールで「地域に光を当てる」ことができるかもしれない。そう思えたからこそ、新しい一歩を踏み出す決心がつきました。
大山:いろいろなタイミングとご縁が合った感じですね。その後2023年の4月からイシン株式会社に入社するということなのですが、最初どのような業務に就くのですか?
渡邉さん:はい、まさに人生の再スタートでした。入社して最初に任されたのは、高知県にある新規拠点の立ち上げです。しかも僕、13年間ずっと経営者で、雇われる経験がなかったので、まず「敬語を使うこと」からのスタート(笑)。現場では、家具の購入一つとっても稟議が必要。ハサミやカッターすら勝手に買えないんですよ。正直、カルチャーショックでした。でも、それも新しいチャレンジだと思えば楽しいもんです。
 イシン株式会社 代表取締役会長の明石智義さん(左)と渡邉さん
イシン株式会社 代表取締役会長の明石智義さん(左)と渡邉さん
大山:勝手が違ったわけですね。例えばどのようなことがあったのですか?
渡邉さん:スケルトン物件を与えられて、自分でオフィスを組み立てるところから始まりました。ダンボールの山を見て「さあ開けよう」と思ったらハサミがない(笑)。コンビニに走って買ったら、「それ、稟議出しました?」って怒られるんですよ。今となっては笑い話ですけど、当時は「え、これでダメなのか」って驚きましたね。自分の当たり前が通用しない場所で、ゼロから再構築するのは、まさに“第2の人生”らしい経験でした。
大山:上場準備中の企業さんですから、当然と言えば当然ですよ、ね。笑
渡邉さん:そうなんですよね(笑)。20代の上司にやんわりと注意されることも多くて。でもそれがすごく新鮮で。自分では“新人として普通にがんばってるつもり”だったんですけど、気づけば動き方が完全に“元経営者モード”。サラリーマンとしての立ち回りがまるでわかってなかったんですよね。最初の数ヶ月は、本当に「これは社会人再教育期間だな」と思うくらい苦労しました。でも、あの戸惑いがあったからこそ、今の自分があるんだなと実感しています。
大山:今、現在どのような仕事ぶりでしょうか?
渡邉さん:現在は大阪に拠点を移し、西日本エリア全体を統括する責任者をしています。経営者支援を軸に、ベンチャー企業のブランディングや「ベストベンチャー100」へのエントリー支援などに取り組んでいます。毎日のように素晴らしい経営者と会い、彼らの想いを世の中に届けるお手伝いができる。まさに“伝える仕事”という意味では、飲食業と地続きなんですよね。
大山:現在の仕事へのモチベーション、どのような想いでお仕事をされていますか?
渡邉さん: 今は「与えられたことを、どれだけ正確に、誠実に返せるか」が自分への課題です。経営者時代は自分の意志で決められましたが、今は違う。だからこそ、目の前の一つひとつの仕事に、丁寧に向き合うことを大切にしています。これが、次のステージへ進むための“助走”になると信じています。
大山:最後に今後の自身の展望についてお聞かせください。
渡邉さん:僕が目指したいのは、「あの人がいたから、この地域が元気になった」と言われるような存在になることです。今は西日本全体を見ていますが、ゆくゆくは地域の力を引き出すような新しい事業を自ら立ち上げていきたい。第二の人生、まだまだ始まったばかりです。もう一度、自分の使命を形にしていく。そんなチャレンジに、ワクワクしています。
編集後記
実は渡邉さんは今でも公私共にお世話になっていて、イシン株式会社に移られてからも経営者を繋げてくれたり、「ベストベンチャー100」にお誘いしてくれたりと交流を続けていました。私は飲食店経営者にもセカンドキャリアがあって良い、そんなふうに思っています。独立した若かりし日と、そこから月日が経ったときにやりたいことが違う、違ってもいいのではないか?とずっと思ってきました。一度しかない人生の中でそんな挑戦ができるような社会になればと思っています。渡邉さんが「今が一番、奥さんが幸せそうです」と言っていたのが印象的でした(笑)。私たちもメディアとして、これからさまざま連携して、地域を応援できるようなことができればと思っています。ありがとうございました!(聞き手:大山 正)