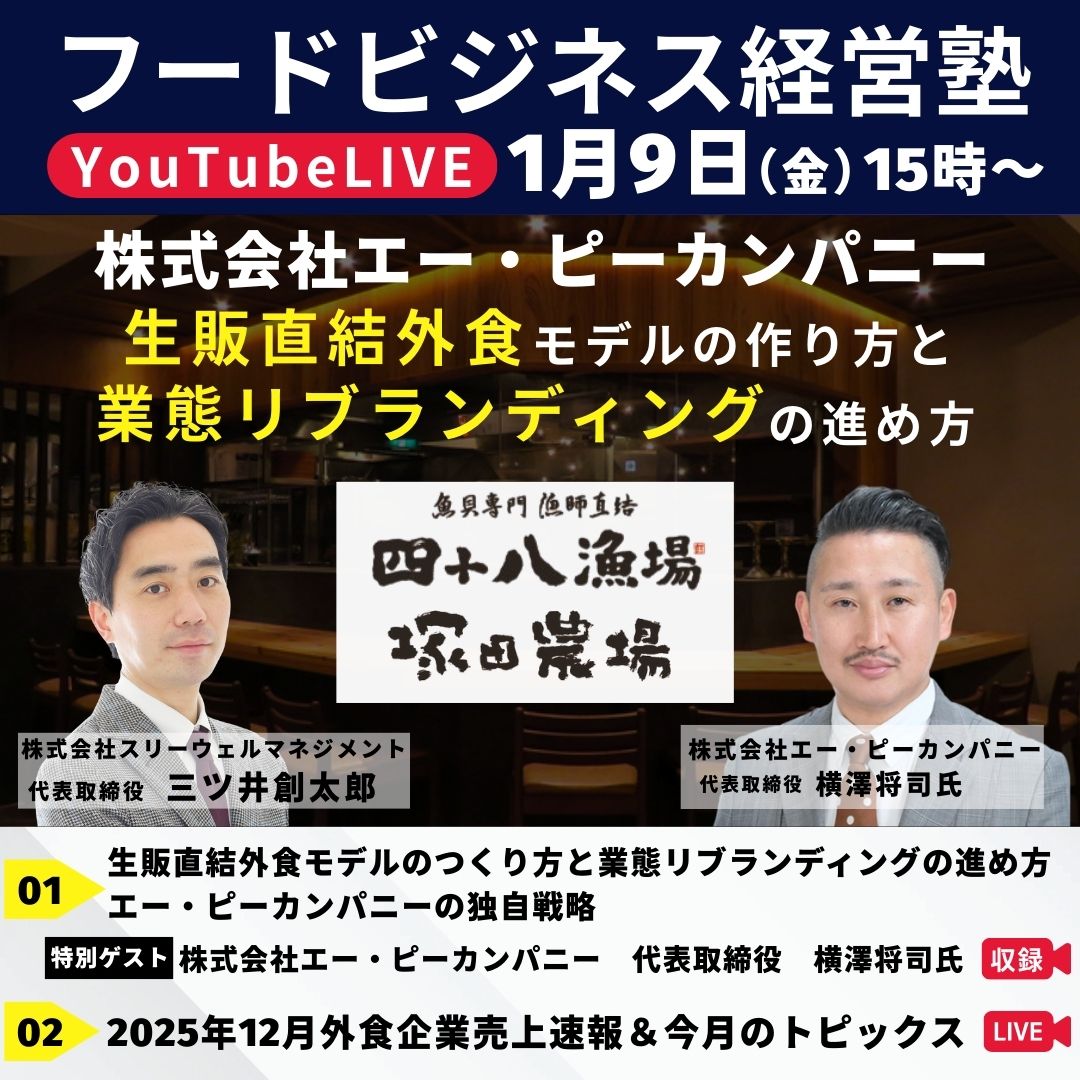女性営業マンが多い「キリン特殊部隊」
マーケティング部に異動した安藤毅は、第3のビール「のどごし生」のブランドマネージャーとなる。2013年秋、徳島から東京へと転勤した。のどごしはキリンの主力商品だ。
その1年後、社内外で特殊部隊との異名をもつ広域販売推進の第2支社営業1部に異動。業務用営業の精鋭として抜擢される。部内では最若手だった。
「個性派揃いだ。怖い人というより、風変わりな営業マンが多い。また、女性が成果を上げている」
安藤は、ぼんやりと思った。営業の世界は実力の世界だ。性別や年齢などは関係なしに、力のある人が高い成績を残していた。
安藤のボスである部長の山本恭宏は、14年4月に着任したばかり。それ以前はキリンヨーロッパに3年間にて、欧州23カ国を営業担当していた。
欧州に赴任する前は、特殊部隊に6年半在籍。キリンの伝説的な営業マンの一人だった。
山本は安藤に言った。
「ここは、それほど厄介なところではない。たしかに、ライバル各社も同じような組織をつくり、大手外食や名店をめぐって我々とぶつかり合う。しかし、競合に勝つ奴と勝てない奴には違いがある」
「違いですか…」
「営業する相手様との、間合いをあけないことだ」
「いつも接していろという意味ですね」
「そういうことだ」
「山本部長、広域販推が営業対象にするのは、上場企業を含めた大きな会社ばかりです。僕が徳島で営業してきたのはみな、小さなお店でした。地域の中で、人と人とのつながりを大切にしていただきましたが、営業のやり方は違うのでしょうか」
「基本は同じだよ。大きなところも、小さなお店も。そして、営業先が大手企業になっても、経営トップには会うべきだ。難しくなるけどね」
「営業する上で、大切だからですか」
「それだけじゃ、ないんだ。企業はトップで決まる。トップがもっているビジョンの中身を知ることが、大切なんだよ。ビジョンに合わせて、我々は提案していくのだから。ビジョン、すなわちなぜ外食を立ち上げたのか、これから事業をどうしていく考えなのか、ホームページを読むだけではなく、できれば肉声で聞きなさい」
「はい…」
「一生懸命働く日本人は多い。だが、将来に対する明確なビジョンをもつ経営者は、意外と少ないのかも知れない。トップと接することでその人を、肌で感じるんだよ。もちろん、トップの人柄やビジョンの中身から、その会社の将来を我々営業マンは判断していく。現実に、いまは数店舗しかなくとも、将来成長していく会社はあるからね」
オーストラリア放浪後、高崎工場を就活目的で奇襲
山本は愛知県出身で、高崎経済大学を卒業して入社したのは1993年。ただし、1年間休学して、オーストラリアの東半分をバックパッカーとして放浪した経験を持つ。現地の農場を巡り、一人でヒッチハイクを繰り返した。最初の4年生になった91年のことで、テレビ番組で『猿岩石』がユーラシア大陸を廻るのより前だった。
「なぜ、バックパッカーをしたかといえば、人生の“決められた線路”のようなものに乗っていくのが、イヤだったからでした。入学時にはオーストラリアに渡り、農作業をしながら一人旅をしようと決めていて、アルバイトでお金を貯めました」
帰国したのは92年4月。世間では就職活動は始まっていた。
しかも、92年入社組まではバブルの余韻から、就活においては学生の超売り手市場だった。このため、学生が他の企業への就活ができないよう「東京ディズニーランドに拘束されていました」(92年入社のキリン社員)という有様だった。
ところが、93年入社の代からこれが一転。就職氷河期へと突入していく。
ということは、仮にオーストラリア一人旅をしなければ、山本はどこの会社にも楽に就職できていた。ビックサンダーマウンテンなどに興じながらである。
山本の父親は商社の営業マンだった。父の背中を見て育った彼は、営業職を志向する。
「たとえ給料が半分になっても、自分はプライドを持ってものを売り歩きたい。その商材は、何だろう」
こう考えたとき、自身が大好きなビールしかないと思えた。特に、オーストラリアの旅で、苦しくなるといつもビールを飲んでいた。
とはいえ、就活には完全に出遅れていた。そこで、山本は思いきった作戦行動に出る。
当時、高崎市内にはキリンの主力だった高崎工場があった(その後2000年に閉鎖)。いきなり山本は、高崎工場を訪問。応対に出てきた総務関係の社員に向かい「キリンビールへの就職を希望します」と告げたのだ。
就活生の奇襲攻撃に工場関係者はみな驚いたが、本社の人事に話はすぐに伝えられる。本社で面接を受け、気がつけば山本は内定を獲得していたのである。
「人生で最初の飛び込み営業は、私にとって高崎工場でした」
入社後、福井県、栃木県で営業し、前述の通り広域推進部、欧州と異動していった。
「山本君とはここでよく会いますね…」の不思議
プレーヤーとして特殊部隊にいたとき、山本は大きな成果を上げる。
ビール4社の製品を扱っている上場するチェーン店を、一番搾りに切り替えたのである。
間断なく、相手先に通い続けた。雨の日も風の日も。時間をかけて、ゆっくりと担当者、そして幹部と人間関係を構築していく。だが、最終的な決定権者である社長とは、最初に名刺交換しただけで、その後の接点を見いだせずにいた。社長の了承がなければ、切り替えなど不可能だ。
しかし、連続して訪問を重ねる営業マンの“姿”を、見ている人はいた。
幹部の一人が囁いてくれた。
「社長はランチで、レストラン〇〇によく行くよ」と。
山本はレストランの隣のカフェで、張り込みを始める。昼食を終え店を出ようとするところを、偶然を装い近づいていく。
「アッ、こんにちは。キリンの山本です」
「やぁ、元気でやっているかい…」
社長が自分の会社のビルに入っていってしまうまでの時間は、2、3分に過ぎない。しかし、この120~180秒に、一日のすべてのエネルギーが費やされた。
一週間の内3回は、“張り込み”と“ぶら下がり”を繰り返した。もちろん、このほかに会えない“空振り”の日もあった。
ここで重要なのは、「決して仕事の話をしてはいけないという点です」と山本。いきなり、「買ってください」と迫ったところで、食事の後の相手は良い印象をもつとは限らない。また、ヨーロッパでは、食事の時にねちっこいビジネスの話をするのは“無粋”であるという考え方がある。「会社ではなく個人を尊重する欧州では、食事の時にビジネスの話はしない。日本の接待とはカルチャーが違う」(欧州事情に詳しいジャーナリストの井元康一郎氏)。オーストラリアにいた山本は、こうした文化を理解していた節がある。
2、3分で交わされる会話は、はとんどが世間話である。仕事の話は一切しない。
やがて、社長は気づく。「山本君とは、ここでよく会いますね…」。日をあけずに世間話ができる背景には、多分野にわたる知識や教養は求められる。ほんの数分であっても、その日により浮上する話題はマチマチだから。
間合いをあけずにトップとの接点を設ける一方、この会社の現場に対してやはり間断なく提案を繰り返していった。
ジワジワと追い詰めていき、契約更新時にビールはすべてキリンへと替わった。