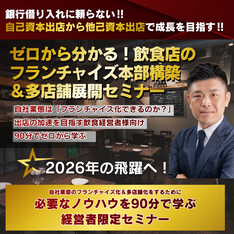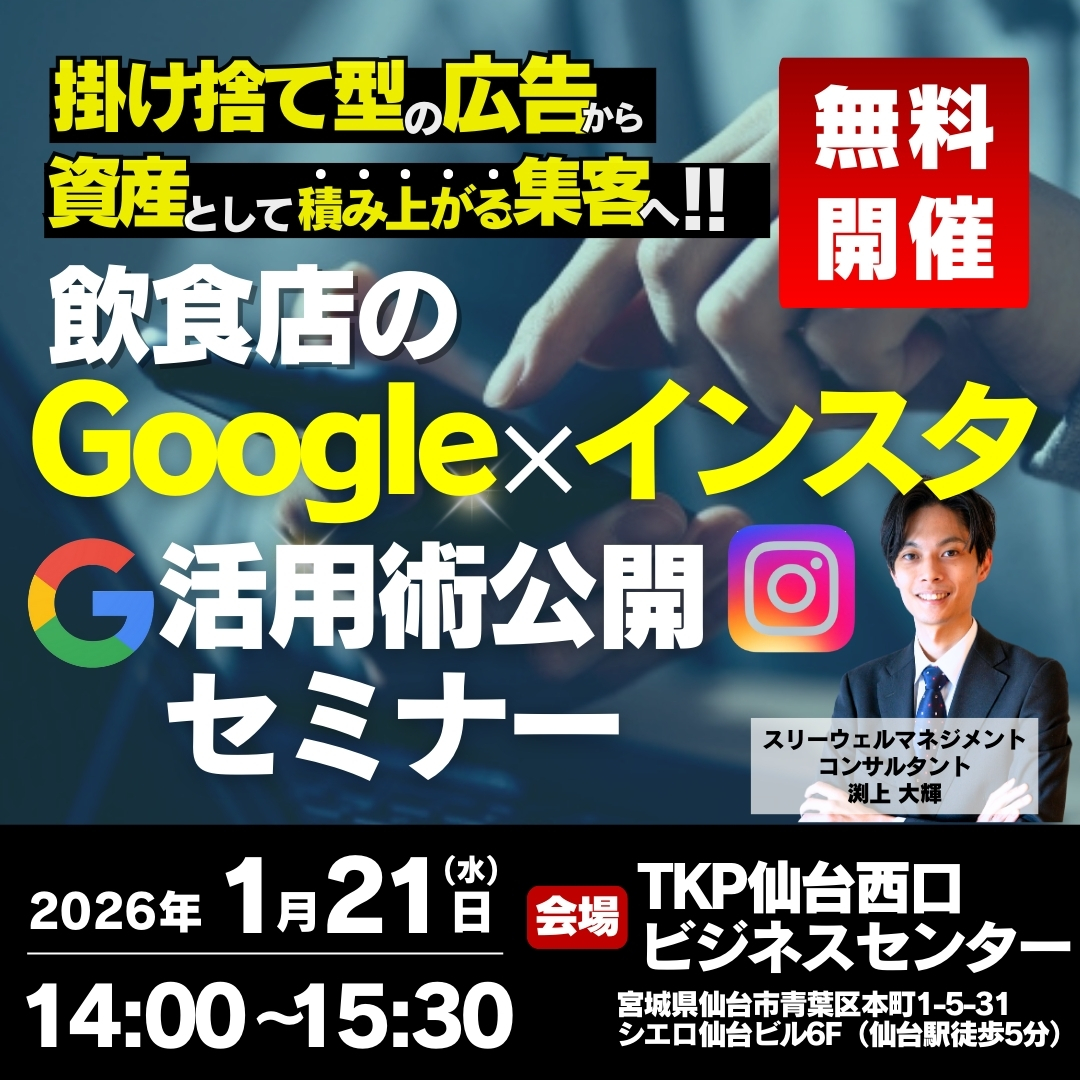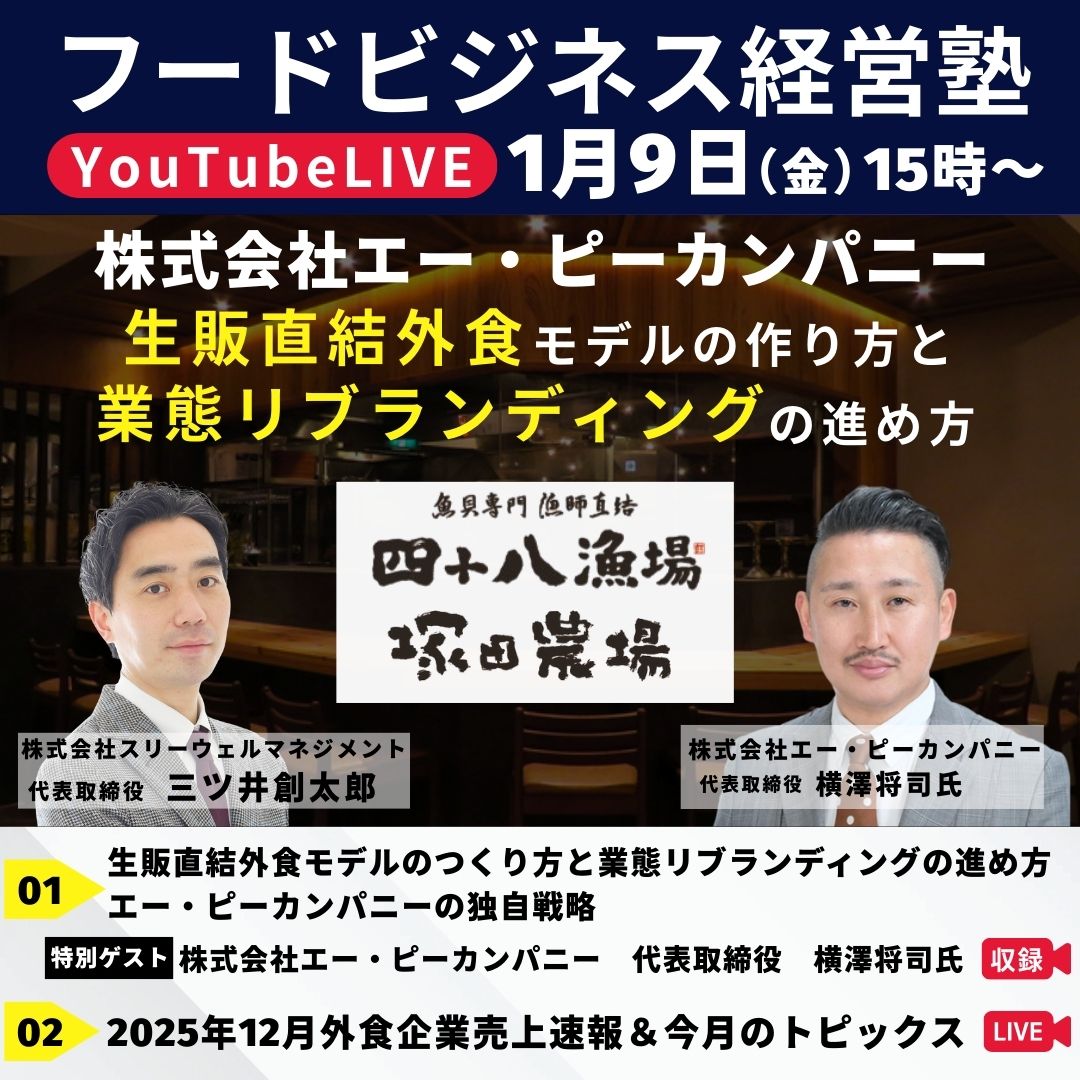大山:2018年の31歳の時に一太朗さんは代表に就任されたとのことですが、それまでの親子四代にわたる歴史の中で、一太朗さんご自身はどのような生い立ちを歩まれ、どのような少年時代を過ごされたのでしょうか?
一太朗さん: まず、親子四代というストーリーですが、厳密に言うと、(ホイッスル三好の)経営は父の代からになります。この親子4代というストーリーは、私の曽祖父が、中国の江蘇省揚州から日本に渡ってきて、その曽祖父を1代目というふうに数えて、私が4代目になるということなんですよ。曽祖父も祖父も、それぞれ中華料理店をやっておりましたので、そのお店の味を食べて育った父が、コンセプトやニュアンスを受け継いで「揚州商人」というお店を創業した、ということになります。

社長室に飾られた親子4世代のヒストリーと、これまでのホイッスル三好のあゆみの年表。
大山:そういうことだったんですね!素敵なストーリーですね。
一太朗さん:私が生まれた頃には、曽祖父と祖父は亡くなってましたので話で聞くしかなかったんですけどね。父から聞くには、二人ともかなり強烈な人物だったそうです。やっぱり日中戦争があった時代背景の中で、今とは比べ物にならないくらい厳しい差別があったりして、本当に過酷な環境を生き抜いてきた。だからこそ、ものすごく精神的に強くなって「起業して見返してやるんだ」という思いで、事業の中に自分の存在意義を見出してそれぞれやってきたというのがあるんです。その家に生まれた父も同じように、自分で事業を興してきたというわけですね。
大山:代々事業家としての精神が、受け継がれているのですね。
一太朗さん:私も小さい頃から父によく言われていたのが「将来、どこに就職するんだ?」っていう話じゃなくて「将来、お前は何をやるんだ?」っていう問いかけだったんです。そういう話を聞いて育ってきたというのが、一つの特徴かもしれませんね。
大山:先代のお父様には2012年に、フードスタジアム主催のセミナーにご登壇いただいたことがあるんですよね。とても豪快かつクレバーな印象の社長さんで、よく覚えてます。
【2012年12月3日開催】フースタ初のラーメン業態研究セミナー! 「ラーメンバルは来るのか?」などをテーマに12月3日(月)第7回フードスタジアム経営戦略セミナー開催!
一太朗さん:そのようですね!その節はお世話になりました。
大山:いわゆる、まさに一太朗さんは社長としての帝王学が元々ベースとして備わっていたわけですね。性格的にはどんなお子さんだったのですか?
一太朗さん:小さい頃は結構内気でインドアでインナーな性格だったので、外で活発に遊んだり特別運動が得意だったりということもなくて、かといって勉強がめちゃくちゃできるわけでもない、本当にごく普通の平凡な子供でしたね。そんな中で「将来何をするんだ?」って父に聞かれて、僕は車が好きだったので、レーサーになりたいなっていう気持ちがあったんです。それともう一つは、父の会社の人たちが、夜も朝もどんな時でも家に出入りしていて、まるで相撲部屋みたいだったんですよ。そこで一生懸命働いているたくさんの大人たちを見て育ったんですけど、その人たちがすごくかっこよく見えたんですよね。当時の社員さんたちが、小さい頃の僕に「大人ってかっこいいんだよ」「大人って自由で楽しいんだぜ」って、いつも教えてくれたんです。だから、僕もレーサーになるか、もしくは父の会社を継いで、かっこいい大人になりたいなっていうことを漠然と思いながら、幼少期や学生時代を過ごしてきましたね。
大山:ということは、ホイッスル三好を継承するという意思が無かった訳ではないんですね!?
一太朗さん:そうですね。 父も「どういう仕事をしたいんだ?」「何をやりたいんだ?」って聞くのと同じぐらい、「いつかお前が継いだらな」というような前提で、僕を育ててきたところがあったので、悪い意味じゃなく僕は植え付けられて育ってきたっていうところがありますね。
大山:そこからどういった経緯で、ホイッスル三好で仕事をすることになるのですか!?
一太朗さん:高校1年生の入学式の夜に、父から「制服を着て待ってろ」って言われて、待っていたら車に乗せられて、赤坂の料亭に連れて行かれたんですよ。部屋に入ったら、当時まだ存命だった祖母が座っていて「一太朗、待ってたよ」なんて言うんです。「何だ!?」って思うじゃないですか(笑)。
そうしたら父から「15歳になったってことは、江戸時代でいえば元服(古代から中世日本においての男子が成人として社会に認められるための通過儀礼)だ。だから今日から俺はお前を一人前の大人として認める。」と言われて(笑)。「いや、今平成なんだけどな…(苦笑)」と思ったんですが、続けて父は「大人として認めるからには、今日を持って(会社を)継ぐ意思があるのかないのか教えてくれ」と言われて(苦笑)。僕はまだレーサーになりたいという気持ちがあったので、「この先、レーサーの道が難しいと分かったら、その時は会社を継ぎたいです」と伝えたんです。そしたら父が、「それは基本的に『継ぐ』っていうことでいいんだな?」って言うんですよ(笑)。父はそういうふうに、話を持っていくのがうまいんですよね(笑)。それを聞いて、横にいた祖母が「一太朗が比呂己の後を継いでくれたら、もう安心して逝けるよ」なんて、泣きながら言うわけですよ。もう、そんなこと言われたら「継がない」なんて言えないじゃないですか(笑)。それで、「分かりました、継ぎます」ってなりました(笑)。

大山:先代三好さん、さすがですね(笑)。「将来は何をするかだ!」と言いながら、決まっていたんですね(笑)。やり手すぎますね(笑)。
一太朗さん:父は僕のレーサーの道は残しておきつつも、その道には絶対に行かせないようにいろいろと手を回していたわけですね(笑)。ただ僕も正直、高校の頃にはそれに気づいていました。やっぱり父の会社もすごく好きだったし、いつかは継ぎたいという気持ちがどこかにあったので、そのことを正面から受け止めて、やっていこうと思ったんです。その後、父に言われたのが「ここからは俺とお前の間に、二つの関係ができる」と。「一つは今まで通りの親子だ。親父には何でも言っていい。ただしもう一つは、先代と後継者という関係が始まる。この関係においてだけは、先代の言うことは絶対だ。一切逆らうな」と。どこかで聞いたことがある「カラスをピンクと言えば…」みたいなことを言われたんですよ。
大山:まさにお相撲さんの世界のようですね(笑)。
一太朗さん:それで、父は続けて「俺がお前に最初に出す5つの指令は、学生時代に5カ所でアルバイトをしろということだ」と言ったんです。それで早速、高校1年生からバイトを始めました。最初はマクドナルドの下北沢店で。当時、マクドナルド全体で3000~4000店舗ある中で、売り上げが15番目くらいのすごく忙しいお店でしたね。
その次に、地元のサイゼリヤのオープニングスタッフをやらせてもらって、その後は僕の会社の「揚州商人」ですね。その後に「ポポラマーマ」、最後に「神座」、という感じで、高校時代にこの5つのバイトをしましたね。
大山:学生さんなのに、めちゃくちゃ働いたんですね!
一太朗さん:それで、大学時代は社内で半分インターンのような形で、ミステリーショッパーの導入を立ち上げたり、いち早くメルマガを導入したりといった、先代から渡されたミッションを訳も分からず、がむしゃらにやっていました。
大山:大学時代からホイッスル三好の内部を知っているわけですね。それはすごい。
一太朗さん:はい。それで、僕も一度は外で働きたいと思っていたんですが、父の体調があまり良くなくて、「すぐにでも会社に入ってほしい」と言われていたんです。そんな中、大学4年生の1月頃に、当時お付き合いのあったコンサルティング会社の代表が、父に「お前の息子を預かってやるよ」と言ってくださって。僕も父に「必ず言われた時には帰ってくるから」と懇願して、9か月間だけですが、外の会社で働かせてもらいました。そして早々に父に呼び戻されて、このホイッスル三好に入社したという経緯です。それが2010年のことですね。
大山:そうだったんですね。それで一太朗さんがホイッスル三好に入られて、最初に改革に取り組まれたことというのは、どんなことだったんですか?
一太朗さん:僕が入社した2010年というのは、実は売上高も店舗数も、ピークだった2006年から下がっている時期だったんです。2006年の売上高の38億4千万円に対し、2010年は28億3千万と、約10億円くらい下がっていて、店舗数も36店舗から31店舗まで減り、社員数もアルバイト数もどんどん少なくなっていく…という、ありとあらゆる数字がマイナスに転じている、下り坂の時期でしたね。
大山:その数字が下がっていった原因というのは、一太朗さんは何だと分析されたんですか?
一太朗さん:原因の例として、2008年頃から始めたメルマガ会員の獲得でした。2010年頃によくやっていた企画として、メルマガ会員さん限定で、平日の水曜と木曜はラーメン全品200円引き、というのをやっていたんです。当時、一番安い塩ラーメンが680円くらいでしたから、480円になれば、そりゃお客様はたくさん来てくれます。瞬間的には。それで、お客様がたくさん来るからといって、毎月とか隔週でこの企画を打ってしまっていたんですよね。それがもう麻薬のようになってしまって、ボディーブローのようにじわじわ効いてきて、逆に200円引きの日じゃないとお客さんが来ないみたいなことになっていたんです。
大山:なるほど。2008年でメルマガ会員の仕組みをやられていたというのも、とても早いですよね。
一太朗さん:そうなんです。メルマガ割引とかはかなり先進的でしたね。僕が入った2010年当時で、会員数が1万数千人くらいいたんです。当時、飲食企業でここまでやっているところは、ほとんどなかったと思います。最終的には35万人くらいまで増えましたね。
大山:すごいですね!これはどういう観点で、導入しようというお考えだったんですか?
一太朗さん:これはですね、当時2006年頃にコンサルティングをお願いしていた会社さんから、「これからは飲食店もメールマガジンを始めた方がいい」と提案されたのがきっかけなんです。まだガラケーの時代ですね。ただクーポンを配信するだけではなくて、「読むだけでためになる、知恵になる、成長感がある」ようなメルマガを送ろう、という企画でした。毎週専属チームがいろいろ考えていて、そこにクーポンを付けることで、成長感とお得感の両方があるから会員数が増えていく、という狙いで始めたんです。
これを会社のミッションとして、トップダウンで各店舗の社員たちにも「とにかくお客さんにメルマガ会員登録をプッシュしまくれ」と指示して、力を入れていった結果、徐々に会員数が増えていったんです。ただ会員数はどんどん伸びる一方で、200円引きクーポンも同時に配っていたので、収益が悪化する、という現象が起きていました。
大山:安さでの来店となると、大手チェーンさんと差別化ができなくなりますよね。
一太朗さん:おっしゃる通りで、資金力で戦ったら僕らは中小企業ですから、大企業には勝てないわけです。それなのに、そこで相撲を取ってしまっているような状態だったんです。そこで僕はお客様に対して、ただ値引きして価値を下げてしまうのではなく、プラスの付加価値を届けたいと、その頃から思い始めたんです。
そこで考えたのが「プレゼント企画」でした。先代に言って、そのために企画室を立ち上げさせてもらって、いろんなプラスワンの企画をやっていったんです。どういうことをやったかというと、当時流行っていた「食べるラー油」があったと思うんですけど、あれの自社版を製造しました。ラーメンかチャーハンを一杯、定価で召し上がってくださったお客様に、その「食べるラー油」を無料でプレゼントする、という企画をやったんです。
これなら、ラーメンや炒飯などのメイン商品の本体価格は値引かないので価値は維持できる。その上で、当時ラーメン屋が間違いなくやっていなかった「食べるラー油」をプレゼントする、ということが話題を呼びまして。全店で千袋くらい用意したんですけど、多分10時間くらいで無くなってしまうほどの反響をいただきました。
大山:それはすごいですね。まさにプラスワンの価値提供ですね。
一太朗さん:2日間のイベントの予定が、2日目にはもう一個も残っていない、という状況でした(笑)。それを当時、父に伝えたら、「これだけ反応があるなら、どんどんやろうぜ」ということになって、そこから「プラスワンプレゼント」をたくさん作るようになりました。例えば、サッポロ一番の塩ラーメンの麺を使って簡単に作れる「揚州商人のスーラータンメンの素」をプレゼントするという企画や、サクマドロップスとコラボして、揚州商人の杏仁豆腐味の飴を作ったりもしましたね。
これまでにやってきたプレゼントの数で言うと、ノベルティーも含めて、おそらく70~80種類はありますね。そういった企画を中心に、お客様との接点を強化してきた、というところです。
大山:素晴らしいですね。先代のお父様は前出の通り「先代の言うことは絶対だ!」と言われていたわけですが、意外と一太朗さんのやられることに素直に取り組まれているような気がするのですが(笑)、そう言った意味でやりやすさみたいなものはありましたか?
一太朗さん:それはありましたね。2008年頃から、父も体力的にはかなり厳しくなっていて、やりたくてもできない部分があったんです。僕もまだ若くて荒削りではありましたけど、動けることはたくさんあったので、父も「やらずに手をこまねいているより、やってみて失敗したほうがまだいい」みたいな話をよくしていたんです。だから、「こういうことをやらせてもらえないか」っていう、僕の積極的な姿勢に関しては、すごく受け入れてくれましたね。
大山:その頃って一太朗さん、23歳とかですよね?若くしてすごいですね。おそらくこのくらいのタイミングで、会社としてのフェーズが変わっているわけですね?
一太朗さん:そうですね。イケイケGOGOの時代は2006年までで、そこから企業としてブランドを確立するっていうフェーズに入りました。実は、「揚州商人」としての直営店の出店は、2006年を最後に、そこから10年近くしていなかったんです。次に店舗を出したのが2015年ですから。店舗数が増えると赤字のお店も出てきますし、父も言っていたんですけど、やっぱりおごりがあったんですね。「一等地じゃなくても、二等地、三等地でも勝てるだろう」と出店したお店が、見事に全部赤字だったりして。そこにリーマンショックであったり、震災、デフレといった社会的な流れもあり、借金比率が高くなってしまって苦しい時期を過ごしたこともあるんですよね。
大山:なるほど、そんな時期があったのですね。その期間に、どういった取り組みをされるのですか?
一太朗さん:まず、「既存店の売上を伸ばそう」ということで、2010年に小皿料理の提供を始めたんです。これをやったことで、まずお客様の層が広がったのは間違いありませんね。うちの店は郊外店も都心型店も商業施設のお店も、老若男女いろんなお客様に幅広くご利用いただいているんですが、どの層からも「ラーメン以外の料理があったらいいのにな」っていう声があったんです。だから、オーソドックスな料理をいくつか置いただけで、お客様にすごく受け入れていただいて、来店頻度が上がり始めた、という実感があります。
あとは「広報」というのを本格的に始めたんです。 ただ企画をやるだけじゃなくて、プレスリリースを出したり、メディアキャラバンをしたりといった中で、そういったニュースソースが世の中に出たときに「お願いランキング」に2013年に出れたことが結構大きなきっかけになって、そこから他メディアへもいろいろ取材が回るようになって、認知とかちょっとずつ上がっていった感じですね。イベントもこの頃にはかなり定着と向上を見せ始めて、メールマガジンのピークは2017年頃だったんですが、その時の最高の会員数は、35万人ほどに達していました。
大山:今でこそ町中華って流行っていますけど、その走りのような仕掛けですね。
一太朗さん:料理は最初、小皿料理だけだったんですが、実は銀座アスター出身の料理長が2011年に入社していて、その人に全店を1店舗あたり4週間ずつ回ってもらって、本格的な料理を現場に落とし込んでもらうということをやりました。料理長はめちゃくちゃ大変だったと思いますけど(苦笑)。そのおかげで、料理のラインナップも、小皿で簡単にできるものから、中華鍋を振って作る本格的な酢豚やエビチリといったものが、全店で提供できるようになったのが2016年くらいですかね。
そういったことを地道にやっていった結果、売上も徐々に伸びていって、2014年からコロナ禍まで、一度も前年の売り上げを下回っていないんです。
大山:それでコロナ禍に入っていくわけですが、揚州商人さんはコロナ禍でも深夜営業を頑張ってされている印象でしたが、当時はどんな感じでしたか?
一太朗さん:2021年10月25日にまん延防止措置が明けて、お酒の提供も再開できるようになりましたが、他の企業さんの中には深夜営業をやめてしまっていて、いざ再開しようと思っても、人手不足で再開が出来なかったというところも多かったですよね。
でも、僕たちはその日から全店で深夜営業も含めてすぐに再開できたんです。これは何でかというと我々、あのコロナが始まった 20年3月、4月の時から社員の給与を基本的にカットしてないんですね。 アルバイトの子たちに関しても、雇用調整助成金を活用させていただき金銭面で不安のない状況にしたんです。 こんな世の中なのでまず安心が大事と思ったんで、そこはガンとしてトップダウンでやりました。
そういった僕たちの姿勢を、社員やアルバイトスタッフの皆さんも感じてくれたんでしょうね。営業再開に向けて、みんながスタンバイしてくれる状況でした。だから、他の会社さんが再開に苦戦している時に、僕たちはスタートダッシュができたという感じです。そのようにV字回復した姿を金融機関さんも評価してくださり、支援につながって、この危機を脱することができたという感じですね。
大山:なるほどです。人が辞めない戦略をとったわけですね。
一太朗さん:辞めるどころか、2020年5月からは外部採用もしていましたからね(笑)。金融機関さんには、すごく怒られましたけど(苦笑)。でも、それはなぜかというと、僕は必ずコロナは明けると思っていたんです。それに、外食産業はただでさえ人手不足で苦労している時に、これだけ採用市場に人が出てくるなんて、めったにないチャンスだと思ったんです。未来に向けて、今やるべきことなんだ、と言って断行しました。誰の賛同も得られませんでしたけどね(苦笑)。そんな逆風の中でも、全部やり切りました。
今は店長の半分以上が、コロナ禍以降に入ってきた人間なんです。もしあの時採用していなかったら、多分今のうちの会社の屋台骨が無くなって、成り立っていないと思います。
大山:鮮やかなほどの逆張りですね。 すごいですね。それで今回、本題のサブスクリプションの話ですが、これはどういう着想で始められたのですか?店舗アプリと連携している感じなんですか?
一太朗さん:おっしゃる通りです。うちがモバイルをはじめとした電子媒体での販促を始めたのは、2008年からなんですね。まだガラケーの時代でしたけど、そこから色々なイベントを打っていきましたが、2018年にアプリに移行した時には、それまでのガラケーのファンのお客様が、「もうアプリがあるんだったら、もちろんそっちに乗り換えるよ」っていう感じで、店舗での訴求にも力を入れていたのでアプリのダウンロード数はスタートから好調だったんです。
ちなみに、2018年にアプリをリリースして今日に至るまでの総ダウンロード数は、150万ダウンロードくらいになるんですよ。
この数字は、同規模の飲食企業のアプリのダウンロード数としては異次元に高いらしくて、当時アプリ開発をお願いしていた会社さんからも「一桁違う」って言っていただけるほど、お客様に評価していただいたんだなと思っています。
それでこれだけファンの方がついてくださっている中で、2019年、2020年ぐらいにはNetflixであったりAmazon Primeといったサブスクリプションが普及していたじゃないですか。 そういった世の中で我々もただのアプリを超える、さらに上級のサービスっていうのをぜひ作りたいな、と思うようになったんです。
大山:なるほど。ただのショップカード機能だけじゃなくて、より上質な機能を持たせたアプリをということですね。
一太朗さん:はい、ヘビーユーザー様であり、ロイヤルカスタマー様がまさに印籠のように「すげえだろ」みたいに出せるようなものを作りたいなぁっと思っていて。 かねてより、コロナ前からサブスクリプション形式で何かできないかなって考えていたんです。月額でお金をいただいて、それ以上の破格のサービスを受けられるものに挑戦してみようと。
大山:サブスクの仕掛けも、また早かったのですね!
一太朗さん:そうですね、当時まだ外食におけるサブスクってすごく少なくて、2020年前後だと僕が覚えてる限りで言うと、ほんと1,2社くらいだったと思うんです。たいていが食べ放題の形式でしたよね。ただ、そうなると「元を取る」っていう意識が働くようで、元を取るハードルが低すぎたり、高すぎたりみたいなところがあって、僕はその辺が難しいなと思ってたんです。元を取るために月に数回来てもらったらお店側が赤字になってしまったり、また来すぎてそもそもそのお店に飽きてしまったり…といったことが他社さんで起きていて、そういった事例を研究・勉強しながらたどり着いたのが今回、我々が提供するプレミアム会員です。
大山:食べ放題となると、確かにそういった問題は出てきますよね。
一太朗さん:我々のプレミアム会員サービスの考え方は、お客様としては今までのメルマガと一緒で、まずラーメンor チャーハンの割引はしませんというところ。 ここがやっぱり肝かなというふうに思ってまして、やっぱり我々ラーメン店ですから、ラーメンの本体価格は割り引くべきではないと考えています。
逆に言うと、それ以外はお客様にお得感を感じてもらえるような内容を考えて、サービス1から、サービス3迄を選んでいただいて「なんと一回の利用で1500円以上お得になりました」というような企画を組んでいます。

大山:これドリンクを飲めば飲むほど、どんどんお得になるじゃないですか!私向きの企画だ(笑)。
一太朗さん:1回で2000円、3000円お得になるのも夢じゃないです。300円払って一回で余裕で元が取れちゃうと。これだけのお得感って他のサブスクと比較してもまあないと思うんで、それが功を奏して元々、揚州商人のヘビーユーザーの方って月1回のご来店位だったんですけれども、それが週1回になったという事例がどんどん出てきています。お客様から一度あたりにいただける粗利額は多少低くなるんですけども、2回以上来ていただければ、粗利の総額っていう意味では、お一人様から少し多くいただけるという意味でお客様からしてもお得なので、まさにTHE Win-Winの関係っていうのをお客様と作っていければと思っています。
ということで・・・
【検証】揚州商人のプレミアム(サブスク)会員は本当にお得なのか!?後日実際に体験してみました。
この日は土曜日で、比較的ランチ時でもスムーズに入店できました。平日は近隣のワーカーさんで、とても賑わっているお店です。

入店すると早速、店内と卓上にPOPがドンっと。

店員さんがプレミアム会員に加入しているかの確認、アプリ加入のおすすめをしてくれます。こういった、やりきる現場力が揚州商人の強みなのでしょう。
プレミアムサービスは3つも!
まずプレミアムサービス1と2を選びます。

私は昼呑みと決めていたので、サービス一は「皿蝦ワンタン」をチョイス。そしてプレミアムサービス2で、ビールを注文。

この時点でまだ皿蝦ワンタンはサービスなので、300円(ビール代のみ)です(笑)。
そして3つ目のプレミアムサービスでおつまみを選びます。

そして数杯飲んで(詳細はラスト、衝撃のお得価格に!)メインのラーメンを注文。

揚州特濃厚塩ラーメンにしよう、とよく見ると、スープの濃度を3倍まで選べるというこれまたユニークな仕掛け。作戦にまんまとハマって(笑)、3倍を注文(通常1倍は、税込1140円)。
鶏白湯の濃厚なスープが麺とよく絡んで美味しかったです。
ちなみに余談なのですが、

黒酢炒飯もめちゃめちゃ美味しかったです(笑)。黒酢と言えど酸っぱいわけではなく、黒酢の旨みを引き出したコクのある黒チャーハン。ボリューミーでがっつり美味しいシグネイチャーメニューといっても良いような逸品です(残りは、お持ち帰りさせてもらいました(笑))。
さて、それではお得な結果発表です。
P会員/皿蝦ワンタン 0(560円お得)
P会員/ピータン 240円(250円お得)
H生ビールジョッキ 300円×2 600円(740円お得)
Hハイボール 200円×2 400円(820円お得)
合計でなんと、2,370円もお得に!衝撃!
補足:今回のプレミアムサービスの肝は、ラーメンまたはチャーハンの値段(価値)は下げずに、常連やファンに対して特典を提供できている点です。(プレミアムサービス適応には、ラーメンorチャーハンの注文は必須)ただ安売りをしているのではなく、看板にも掲げている「ラーメン」の価格を下げずに顧客接点を作るというサブスクのお手本のようなサービスだと思いました。私のように呑み客にとってはもっともっとお得になる可能性も大(笑)。昼から通し営業のため、早い時間の昼呑みなどの際に利用したいとリアルに思いました(笑)。
インタビュー続き
大山:今後の一太朗さん体制におけるホイッスル三好は、会社としてどういうふうにしていこうというのはありますか?
一太朗さん:すごく大切だと思っているのは、人間味を感じられる中華屋であるということだと思っています。私はロボティクスなどの否定派ではないんですけれども、やっぱり飲食店に行く醍醐味と言ったら「日々疲れてる」とか「ストレスが溜まっている」というようなことの憂さ晴らしであったり、楽しい気分をより楽しくするというのが、外食の根幹の立ち位置だというふうに思っています。AIやロボティクスが進んできた昨今だからこそ、ヒューマニズムみたいなものが価値を増していくと思うんですね。日本全体においても、少子高齢化や労働人口の減少という中で、採用などは確かに難しくなっていくと思うんですけれども、この一番難しいところに真正面から当たって、我々がお客様にとって価値のある店舗営業ができると、お客様の喜びって何倍にもなると思うんです。逆に言うと、発注であったり裏方の人がやらなくていい仕事については機械化・システム化、自動化を進めて、人間が人間として働く価値のあるところだけに、すべてを集中できる業務体制の変革を行なっていきます。
大山:まさにDXは、人間のやるべきことを洗い出すためのツールに過ぎないということですね。
一太朗さん:あと今、インフレの最中なので第一次産業への参入というところも考えているところです。うちが一番使うのは小麦と米と豚肉と海老なのですが、さすがに漁業と養豚は難しいんでしょうけれども、農業の世界に参入して仕入れコストを安定させるというのはとても重要だと考えています。
弊社は売り上げに関しては、比較的順調に推移していますし、採用においても他社さん以上にはうまくいっている方だというふうには思いますが、会社の中におけるPL構造を考えてみたときに、やはりアキレス腱となるのが原価なんですよね。これからどんどん食材原価は上がっていく可能性がある中で、このアキレス腱=リスクを減らすためには一次産業の参入が肝になってくるのではと思っています。必ずしも自分たちが農業を1から10までやるっていうことでなくても、契約農家さんと取り組むであったり。 多少市場価格より高くても自分たちでも食材を確保してやっていくということの大切さを、インフレ下で初めて身をもって感じています。
大山:最後に具体的な店舗数や売上高、その他展開についての目標は定めていますか?
一太朗さん:はい、定めています。まずはコロナ禍で傷んだ財務を立て直すために、今年来年は直営の出店を年2,3店舗計画しています。それと 2018年に全て終了したフランチャイズの企画についても、元々その業界に見識のある人材を営業本部長に招いてスタートをしているところです。ただこれは初期費用の持ち出しのないものなので、財務がどうということではなく、やりたい企業様がいれば挑戦しようといった感じなのですが、向こう2,3年でフランチャイズ含めて年間4,5店舗出せれば十分かと思っています。加速度的に出店をしていくというより、やはり1店舗1店舗のクオリティーをしっかり作っていくという方がよほど大事かなというふうには思っているので。ただ先代が100店舗という目標を持っていたので、我々2024年に発表した10年構想の事業計画で2034年には100店舗になれるよう、クオリティーを大切に日々営業していくことを目標にしています。あと、食文化への貢献ということを考えると、2,3年後を目処にドイツやフランスといった欧州に出店していきたいと思っています。
大山:素晴らしいです!本日はお時間いただきありがとうございました。
編集後記
初めてお会いした二代目社長の一太朗さん。爽やかで流暢な語り口、記事をテキストベースで読むと「めちゃめちゃインテリなビジネスマン!」という人物像を思い浮かべると思いますが、それだけではなく気さくで接しやすい、そんなキャラクターの持ち主です。豪快に先頭を切って船を先導するキャプテン的な存在が先代の比呂己さんだとすると、船員たち全員の意見を吸い上げ、緻密に進行方向を計算し帆を進める頭脳派リーダーが一太朗さん、そんなふうに思いました。これまで何となく寄らせてもらっていた揚州商人さんでしたが取材後、すっかりファンになっていました。これももしかしたら天才軍師・一太朗さんの策略なのかもしれません(笑)。今後の同社の未来に、注目していきたいと思います。(聞き手:大山 正)
◾️こちらの企業に興味・関心、講演依頼、各種コラボレーション等、連絡を取りたい方は下記フォームよりお問い合わせください。弊社が中継し、ご連絡させていただきます。(各種コラボレーション、メディア取材、商品サンプリング等)