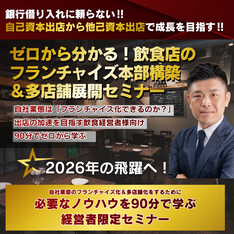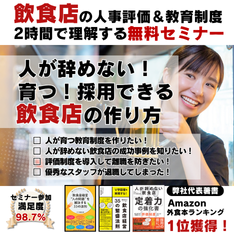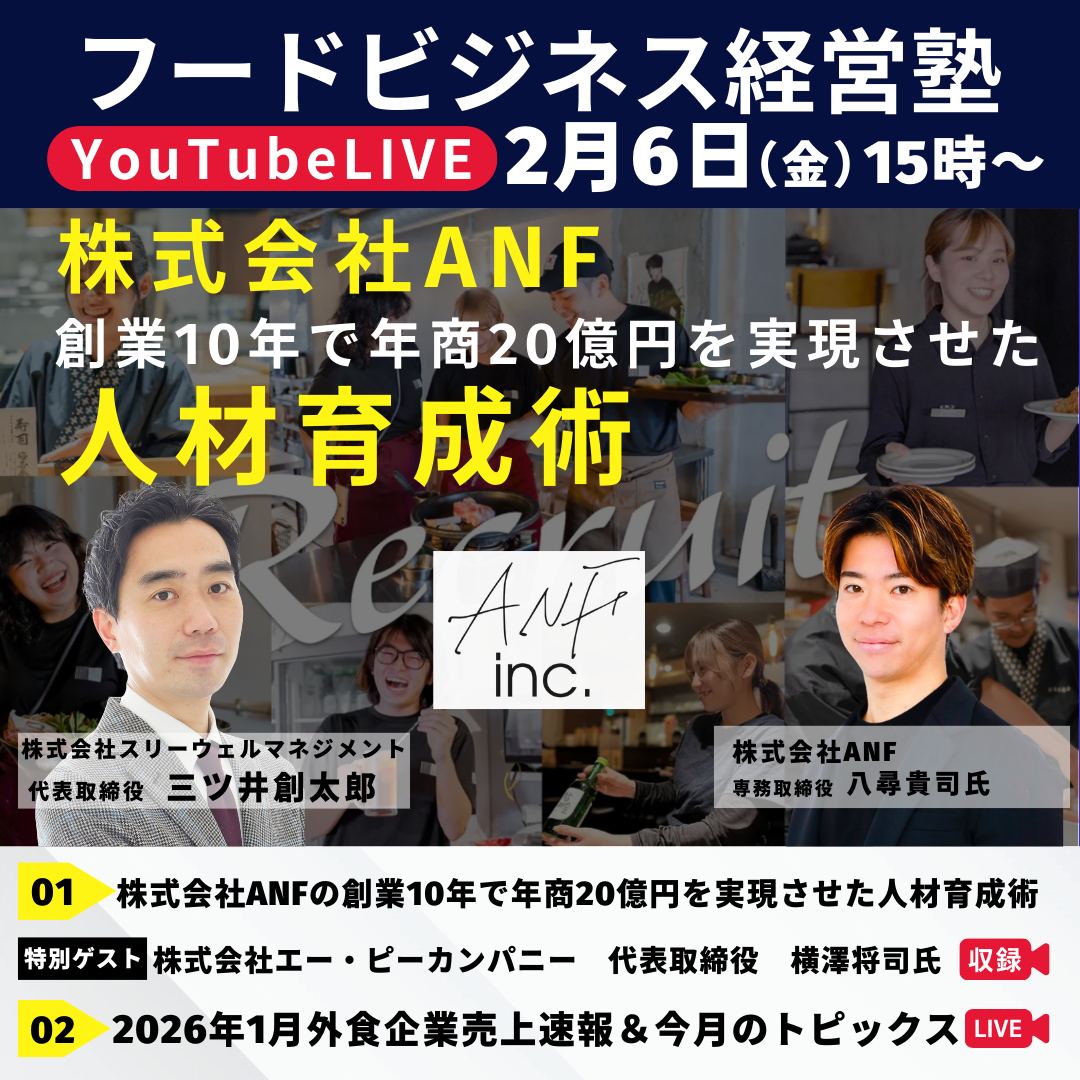株式会社おすすめ屋 代表取締役CEO 加藤誠庸氏:1984年、神奈川県横浜市生まれ。東京理科大学で統計工学や生産管理を学ぶ。在学中に飲食店でアルバイトを経験。卒業後に飲食店に特化したWebコンサルティングの会社を設立。2015年、31歳の時に東京・八王子に「おすすめ屋」の1号店を開業。
株式会社おすすめ屋 代表取締役CEO 加藤誠庸氏:1984年、神奈川県横浜市生まれ。東京理科大学で統計工学や生産管理を学ぶ。在学中に飲食店でアルバイトを経験。卒業後に飲食店に特化したWebコンサルティングの会社を設立。2015年、31歳の時に東京・八王子に「おすすめ屋」の1号店を開業。
“専門店”に勝機を見出し、破格の2000円で圧倒的に勝つ!
Q:加藤社長は理系の大学で経営工学などを学んだそうですが、そこからどういった経緯で飲食業界に進むことになったのですか?
自分は横浜市の戸塚出身で、大学時代に地元の飲食店でアルバイトをしていました。飲食店の仕事に特別な思い入れがあったわけではなく、大学生のアルバイトと言えば飲食店が当たり前だったからですが、ITをきっかけに飲食業界に進むことになります。
当時はちょうど、ホットペッパーが紙媒体からWeb媒体に切り替わる時期でした。パソコンでプログラミングやホームページを作るのが好きだった自分は、アルバイトをしていた飲食店にWeb販促を提案して成果を上げました。そうして大学卒業後、飲食店に特化したWebコンサルティングの会社を立ち上げたのです。そして2011年、この会社のクライアントだった横浜の焼鳥店を引き継ぐ形で初めて飲食店を経営しました。これをきっかけに飲食店経営で勝負してみたいという気持ちが強まり、2015年に食べ飲み放題2000円の「おすすめ屋」を八王子に開業しました。
Q:食べ飲み放題2000円は衝撃的な安さですが、まず食べ飲み放題の業態にしたのはなぜですか?
Webコンサルティングは、検索ワードなどからどんな飲食店が求められているのかを分析するのが仕事の一つだったので、若い人を中心に食べ飲み放題の需要が結構なボリュームであることは分かっていました。実際、大手の居酒屋チェーンでも食べ飲み放題をやっていました。ただし、食べ飲み放題をメインにはしていません。あくまでもメインはアラカルトで、食べ飲み放題は片手間でやっている印象もありました。
そこで、食べ飲み放題の専門店にして、その魅力をとことん追求した業態にすれば勝機があると思ったのです。飲食店を経営するからには、店舗展開して会社を成長させたいという目標を当初から持っていたので、後発のチェーンでも大手に勝てる業態として食べ飲み放題の専門店にしました。
Q:なるほど。それにしても2000円は破格ですね。なぜ、この価格に?
一言で言えば、圧倒的に勝つためです。安い居酒屋を探している人は2000円~3000円で検索します。その最安値である2000円で、しかも食べ飲み放題であれば、間違いなく大きなインパクトを与えることができます。
Q:おっしゃる通り、すごいインパクトですが、最初から2000円で利益を出すことができたのですか。
1号店は思ったよりも原価率や人件費率が高くなってしまい、売上が目標の800万円に達してもほとんど利益が残りませんでした。しかし、人件費率が高かったのは、居抜き店舗のために作業動線のムダが非常に多かったからです。2号店の上野店はスケルトンから店舗を作って動線を改善したので、人件費率がガクンと下がりました。その後もモバイルオーダーの導入などで人件費率は下がり、現在は21~22%くらいです。
一方、原価率に関しては、メニューの内容を何度も見直しながら徐々に下げていった感じです。その結果、以前は40%を超えていた原価率も、現在は35%におさまっています。

何を食べ飲みしても、2000円(税込2200円)という衝撃の価格設定
「お客様とお店がWin-Win」になるようにメニューを設計
Q:現在のフードとドリンクは70品・70種が基本だそうですが、食べ飲み放題のメニューで特に大事なポイントは何ですか。
安いだけでなく、より良いものを提供してお客様に満足してもらうことが大事ですが、当然ながら、お店としては利益を出さなければなりません。そうした中で重要なのは、いかにして、お客様とお店がWin-Win(ウィンウィン)になるようにするかです。
例えば、居酒屋では辛いものが好きな人向けのスピードメニューとしてキムチとチャンジャの両方を提供しているケースが多くあります。しかし、チャンジャはキムチに比べると原価が4、5倍かかる。仮に食べ放題の「おすすめ屋」でチャンジャを提供し、そればかり注文されてしまうと、お客様が「勝ち過ぎ」、お店が「負け過ぎ」の商品になってしまいます。しかし、実際にはチャンジャをメニューから外し、キムチだけしか提供しなくてもお客様は満足してくれています。お客様が満足し、原価も高くないキムチはWin-Winの商品なのです。
同様に刺身であれば、マグロはお客様が「勝ち過ぎ」で、比較的、原価の低いカツオの刺身がWin-Winです。他にも若い人が大好きで、なおかつ原価が低いポテトフライ(「北海道醤油バター」、「ガーリックバター」等のフレーバーを用意)や、鶏モモ肉メニュー(「韓国プルコギもも焼き」、「黒胡椒&ガーリックもも焼き」等)もWin-Winの代表的な商品です。
Q:「おすすめ屋」はもつ鍋や鶏鍋を食べ放題で楽しめるのも魅力ですが、鍋料理の原価はいかがですか。
鍋に関しては、1人前で約200円の原価がかかります。2000円のうちの200円なので原価としては高めで、お店が少し負けている商品です。しかし、コスパの高さをより感じてもらうには、敢えてそうした商品を提供することも必要だと思っています。また、もつ鍋や鶏鍋は食べ応えがあります。そのため、鍋を注文すると他の料理の注文数が減り、結果的に鍋を注文したもお客様も、そうでないお客様も原価はさほど変わりません。
Q:飲み放題のドリンクについてはどうですか。
ご存じのようにサワーやハイボールは原価が低く、ビールは原価が高い。そのため、税込2200円の食べ飲み放題にビールは付けていません。税込2500円でビール付きの食べ飲み放題も選べるようにしていますが、注文の約9割の税込2200円の食べ飲み放題です。来店客の約8割を占める20代のお客様があまりビールを飲まないため、ビールが付かない税込2200円の食べ飲み放題が主力になっているのです。
また、サワーの焼酎や割材などには、誰もが知っている大手メーカーの製品を使用して、そのブランド名を目立たせています。値段が安い食べ飲み放題であっても、信頼できる製品を使っていることを分かりやすく伝えるためです。
Q:税込2500円で卓上レモンサワー付きの食べ飲み放題にしている店舗もあります。卓上レモンサワーを設置するかどうかは、どんな基準で決めているのですか。
税込2200円の店舗が70~90席程度であるのに対し、卓上レモンサワー付きの税込2500円の店舗は130席や150席。「席数が多い店舗は設置する」という単純な基準で決めています。席数が多くなると、どうしてもドリンクの提供が遅れがちになるため、お客様に自分で注いでもらえる卓上レモンサワーを設置しています。

席数が多い店舗は、卓上レモンサワーを設置している
実は店名もSEO対策!コールセンターで席の稼働率も上げる
Q:食べ飲み放題2000円の破格値で利益を出すのは簡単ではありません。にもかかわらず、成功している理由としては、他にどんな点がポイントになっていますか。
「おすすめ屋」のお客様は、食べ飲み放題目当ての目的来店です。目的来店であるため、家賃の安い空中階でも集客できるのが「おすすめ屋」の大きな強みになっています。実際、他はキャバクラしか入っていないビルの5階や⑥階、あるいはエレベーターのない3階といった空中階でも成立しています。
Q:具体的に家賃はいくらですか。
店舗によって差はありますが、例えば上野店は47坪で月商900~1000万円を売りながら、家賃は43万円と坪1万円を切っています。50坪で月商1400万円以上と特に売上がいい歌舞伎町店も、家賃は歌舞伎町としては格安の107万円、およそ坪2万円です。
Q:FLRのRがそれだけ低いと、確かに利益を出しやすくなりますね。しかし、空中階だと店の宣伝もしづらいため、無名の開業当初はさすがに集客に苦労しませんでしたか。
さほど苦労しませんでした。その理由の一つとして、実は「おすすめ屋」という店名自体がSEO対策になっているのです。「おすすめ屋」という店名であれば、ネットで店を探す人が「食べ飲み放題 おすすめ」というワードで検索した時に上位に表示されます。店名を「おすすめ屋」にしたのは「みんなにおすすめしたい」という意味もありますが、一番の理由はこのSEO対策で、実際に大きな効果がありました。
Q:ITに強い加藤社長ならではの巧みな戦略ですね。
「おすすめ屋」の1号店を出店してから3、4年後には、予約受付のコールセンターも設けました。目的来店だとほぼ予約での利用になるため、予約の受け方を工夫してムダなく席を稼働させることが売上の最大化につながるからです。
「おすすめ屋」の食べ飲み放題は基本的に2時間制で、店舗の営業時間は23時までです。そのため、例えば19時スタートの予約を取ってしまうと2回転させるのが難しくなるため、18時スタートや18時30分スタートから予約を取っていきます。また、2名客を4名席に入れると席の稼働率が落ちるため、ギリギリのタイミングまで2名客の予約に対して4名席は解放しません。
予約受付の専門部隊であるコールセンターを設けることで、これらの調整を店舗ごとにきめ細かく行い、高い精度で席の稼働率を上げているのです。現在、予約はネットが7割で電話が3割。コールセンターのスタッフが電話対応だけでなく、ネット予約にも対応しています。コールセンターを設ければ、当然、そのための人件費はかかりますが、現在、「おすすめ屋」の1日の予約客の数は21店舗全体で1000組以上にもなります。確実に人件費以上の売上効果があり、コールセンターで蓄積した予約受付の仕組みが独自のノウハウにもなっています。

「おすすめ屋」という店名自体がSEO対策との事。コールセンターの活用も独自戦略
FCでも出店地域を拡大し、50店舗を目指す!
Q:一般的に居酒屋では、4名席に2名客が座っているケースなどが多いため、いわゆる“満席”であっても実際に埋まっている席数は7~8割程度です。コールセンターで席の稼働率を上げている「おすすめ屋」は、もっと埋まるということですか。
はい、そうです。例えば150席の店であれば、ピーク時は約9割の130席以上が埋まることも珍しくありません。
Q:それはスゴイですね。ムダな席がないパツパツの繁盛ぶりで、それだと生産性も上がりそうです。
客席だけでなく営業時間のムダも少なくできています。23時までの営業で2回転させることができるため、営業時間を深夜まで延ばす必要がないのです。それに合わせて労働時間も短くすることができています。営業時間が23時までで、毎日の仕込みも早くて15時からなので、社員の月の残業時間は10時間を切っています。人材難の時代だけに、この効果で社員の人材を獲得しやすいのも大きな強みになっています。
Q:料理提供のオペレーションに関しては、生産性を高めるためにどんな工夫をしていますか。
仕込みをしっかりと行い、営業中の調理の手間を極力減らすようにしています。そのため、仕込んで皿に盛った料理を並べて冷蔵できるリーチインショーケースを活用しています。店舗によっては、1.2m幅のリーチインショーケースを2台導入しています。また、客席の手前まで料理を運ぶ中間配膳には、配膳ロボットも活用しています。
Q:「海鮮とおでん 食べ飲み放題 おすすめ屋 PREMIUM」の展開を今年からスタートしたのは、どんな理由からですか。
すでに「おすすめ屋」があるエリアに出店しても、カニバリしないようにするためです。実際、税込3300円のPREMIUM業態は、税込2200円よりも約1000円値段を上げただけですが、客層がガラリと変わりました。値段を上げて商品の内容を一層魅力的にすれば、30代以上の客層においても食べ飲み放題の需要が大きいこと分かりました。店名に掲げた「海鮮とおでん」の看板商品として提供している「海鮮刺身升盛り」や「茹でタンおでん」が好評で、業績も好調です。
Q:最後に今後の目標について教えてください。
現在、「おすすめ屋」は東京、神奈川、千葉、埼玉の他に、名古屋、京都、神戸、熊本にも展開しており、熊本下通店は地元の外食企業が経営するFCです。基本は直営での店舗展開になりますが、今後はFCでも出店地域をさらに拡大していきたいと考えています。店舗数はまずは50店舗を目標にし、上場も目指します。
Q:今後の展開にも注目しています!今日は「おすすめ屋」の成功の秘訣について、興味深いお話をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました。
取材・執筆:亀高 斉
1968年生まれ。岡山県倉敷市出身。明治大学卒業後、1992年に㈱旭屋出版に入社し、1997年に飲食店経営専門誌の「月刊近代食堂」の編集長に就任。以来17年間、「近代食堂」編集長を務め、中小飲食店から大手企業まで数多くの繁盛店やヒットメニューを取材。2016年に独立し、フリーとして活動。取材・執筆の他、書籍の企画・編集も手掛けている。趣味は将棋。