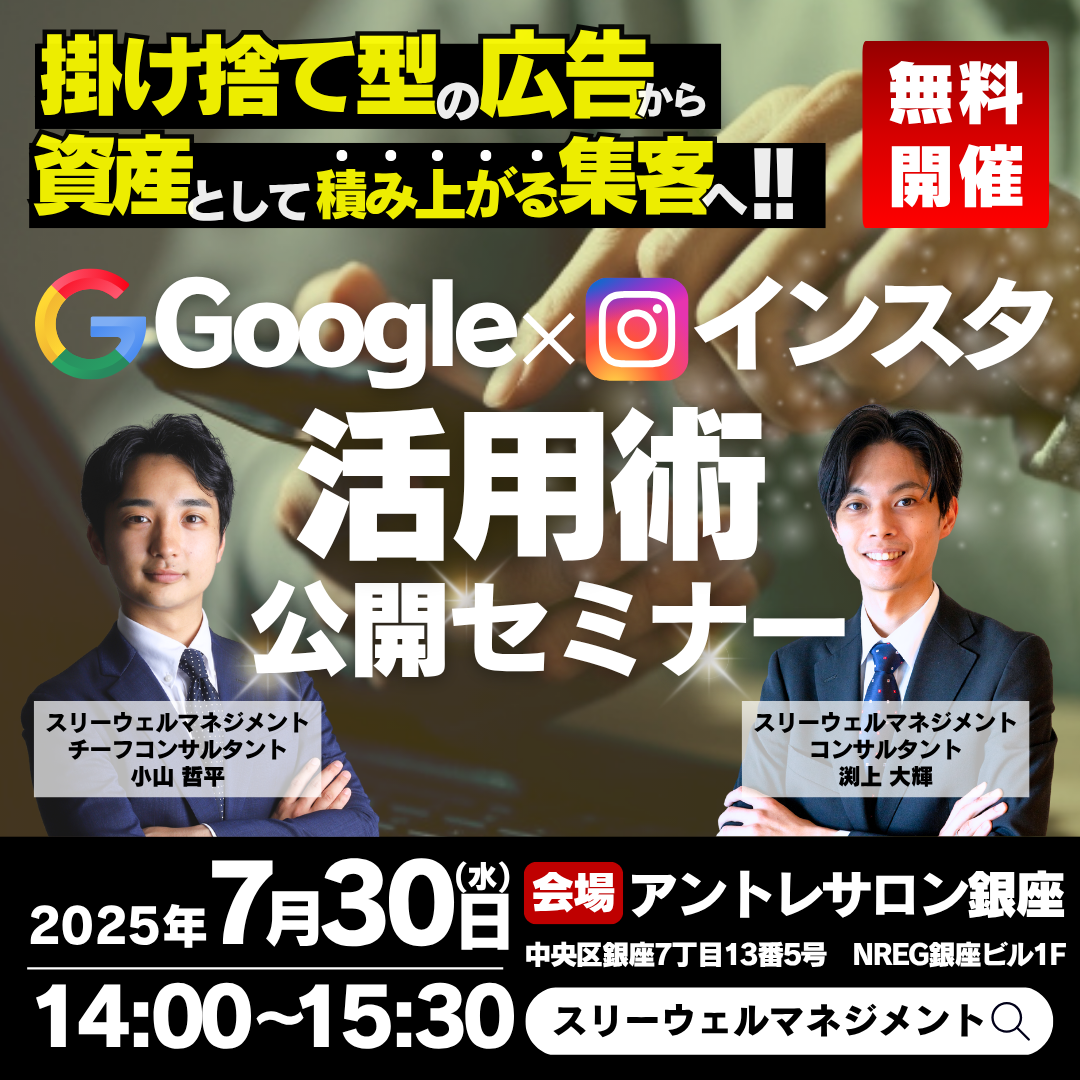悲願のサンウエーブキッチンテクノ買収
テンポスバスターズ(以下テンポス)は、今年4月、LIXILグループから、業務用厨房設備機器の設計・製造・販売のサンウエーブキッチンテクノ(本社:東京都新宿区、売上高50億円、以下サンウエーブ)を買収した。買収金額は3億3000万円。サンウエーブといえば「総合キッチンマネージメント企業」として、日本マクドナルド、サイゼリヤ、ワタミ、松屋フーズなど大手や中堅の飲食チェーンに納入実績のある由緒正しい企業だ。
テンポスも中国・上海に工場を持ち、食器洗浄機などプライベートブランド(PB)商品を製造、輸入販売している。近年では店頭ではPB商品の売れ行きが良く、リサイクル厨房機器の構成比は売上高(14年4月期見込180億円)の20%程度まで縮小している。といっても稼ぎ頭はリサイクル厨房機器であることに変わりはないが、厨房機器業者としては実力不足であった。
テンポスは業務用厨房機器業界からは異端者扱いされ、「暴れ者」」「ならず者」と冷ややかに見られて来た。だがサンウエーブの買収によって、テンポスはようやく既存の業務用厨房機器メーカーの背中を捉えることになった。
「サンウエーブの買収は長年の悲願だった。当社は個人経営など中小零細の飲食店が主要顧客であり、多店舗展開する中堅以上の飲食店チェーンに食い込めなかった。顧客の要求するグレードのデザイン・設計ができないことと、外販という攻めの営業ができなかったからだ。だがサンウエーブはそれができる。また、大手・中堅飲食チェーンなどに納入実績があり、これで当社も大手・中堅の飲食店チェーンにも営業を広げることができる。何よりも心強いのはサンウエーブには100人近い営業部隊がいることだ。これまで当社は店舗での“待ち商売”で営業は全くやってこなかった。そのため初めて来店されるお客さんには商品を買ってもらえたが、2回目、3回目となると営業部隊を持つライバルの厨房機器店に顧客を奪われてきた。しかし、新しく営業部隊が加わることになり、これで全国45店舗の情報網などを活用、営業部隊と店舗が連携して“攻めの商売”ができる」(森下氏)
テンポスはサンウエーブの買収によって売上高は単純合算で240億円規模となる。来年3月の「あさくま」の上場に加え、合併による相乗効果などで15年4月期で売上高300億円を見込んでいる。一方、M&Aでシンガポールに進出する計画も進行しており、森下氏は「3年後には500億円企業を目指す」と鼻息も荒い。
森下氏の起業の原点を探る
 初めに森下氏がテンポスバスターズを創業するまでを簡単に振り返ろう。
初めに森下氏がテンポスバスターズを創業するまでを簡単に振り返ろう。
森下氏は静大教育学部を6年かけて卒業。71(昭和46)年4月東京電気(現・東芝テック)静岡支社の現業社員(中途社員扱い。組合員ではない)として採用された。東芝テックは森下が静岡支社に入社した71年6月、新製品の電子レジスター「マコニック」を新発売した。当時、レジスターは米国のNCRかスウェーデン製のスエダの時代、日本製は耐久性に劣り、スーパーマーケットなどではまだ全く取り扱わなかった。
セブン-イレブン・ジャパンが第1号店の「豊洲店」(東京都江東区)を開店したのが74年、POS(販売時点情報管理)システムを開始したのは82年のことだ。森下氏はスーパーマーケット(以下スーパー)など流通業界の情報革命が本格化する少し前に東芝テックに入り、営業マンとしてスタートした。東芝テックに入社した年に静大の同級生と結婚した。森下氏は、「学生時代、チャランポランで情けない男だった」というが、家庭を持ったことで責任感が芽生え、我慢強い男に変身した。
しかしながら、入社してから6ヵ月間は1台も売れなかった。入社後科学的なアプローチやセールストークなどを研修し、飛び込みで営業に入ったが、中小企業の社長などから全く相手にされなかった。森下氏はこの危機を何とか乗り切ろうと、東芝テックのトップセールス3人に恐る恐る電話し、鞄持ちで営業に同行させてもらった。ここで「営業とは人間と人間との勝負だ。人間を落とさなければダメだ」ということを学んだ。
「一人は地場スーパーのバックヤードに50万円、50キロする重いレジを持ち込んでコンクリートの土間に背広を着たまま土下座。『何とか買ってくれ』と4時間も土下座しっ放し。最後は店主が、『レジを置いてゆけ』と折れた。もう一人は新式の電卓の売り込み。顔見知りの水道屋の社長の引出しからハンコを持ち出して押すと、ここにサインしてくれと脅迫まがいの売り方で売ってしまった。もう一人のセールスのやり方も似たり寄ったり。彼らはセールストークなどとは全く無縁、ひたすら相手の感情に訴える作戦。3人に共通していたのは、人間をよく知っていることだった」
彼らは科学的アプローチなどとは無縁の独自の営業スタイルを展開していた。森下氏は自著『「戦いモード」で会社が変わる 実践!「武士道」の成功法則』の中で、次のように述べている。
〈セールスの成熟段階にもよるけれど、最後のところは、合理性ではない。人間との勝負なんだ。結局、「正しいこと」を伝えるのではなくて、その人のレベルに合わせて、納得してもらうことが大事だったのだ。要は、人を落とさないとダメだとわかった〉
こんな時期を経て森下氏は営業マンとして頭角を現していった。やがて全国展開するスーパーに食い込み、入社3年目には全国10位の成績を上げ、部下が2人就いた。「部下が就いたら俄然やる気になった」(森下氏)という。親分肌のところがあった森下氏は、入社4年目28歳の時には課長代理に昇進、6人の部下を動かしトップセールスに就いた。その結果、現業員としては異例の出世で当時の社長の引きで東京本社の営業本部勤務となり、課長に抜擢された。以後、スーパーなどを主要な取引先としてトップセールスを3年続けた。「営業改革の旗手とおだてられ、天狗になり、やりたい放題だった」(森下氏)という。
森下氏の営業スタイルは大胆不敵だった。大口のスーパーと取引しているのを武器に担当者が要求するものは、東芝テックの製品でなくても何でも販売した。例えば担当者が「3000万円する冷蔵ケースを入れたい」といえばメーカーに話しを付けて冷蔵ケースを販売し、10~15%のマージンを稼いだ。電子レジスター5台売るのと比べ販売マージンは桁違いに大きく、森下氏の大きな手柄になった。森下氏の課は“社内の商社”といえる存在になった。
「スーパーの出店に合わせ、営業本部に断りなく岩手県に北上営業所、関西に滋賀東営業所というのを勝手に作った。部下をアパートに住まわせ、そこを営業所と名乗らせ、そのルートで寿司ロボットやおにぎりの機械などを販売しマージンを稼いだ。東芝テックには仙台に営業所があるが、ある時組織上存在しない北上営業所が仙台支社にバレてしまい、ひと騒動あった。上司から『タダの課長が営業所を勝手に作るとは何事だ!』と、厳しく弾劾され、始末書を何枚も書かされた」(森下氏)
それでも営業成績が順調なうちは役員たちも森下氏の傍若無人の営業活動を我慢して見ていた。だが森下氏を抜擢した社長が異動し、そのタイミングで業務上のちょっとしたミスを起こすと、直ぐに退職を迫られた。それを無視していると今度は解雇通告された。“森下解雇”のシナリオが出来上がっていたようなのである。こうして森下氏は入社8年目の79年頃東芝テックを辞めた。32歳の時のことだった。しかし、森下氏は東芝テック時代にトップセールスを続け大きな収入を得ていた時、将来への不安から貯蓄に励みまた株式投資などによる資産運用に励み、1億円近くの貯金をしていた。
森下氏がけた外れのサラリーマンであったことは確かである。
業務用食器洗浄機メーカーのKyoDo設立
 東芝テックを辞めた後、森下氏は本来なら独立開業に踏み切ってもおかしくはなかった。
東芝テックを辞めた後、森下氏は本来なら独立開業に踏み切ってもおかしくはなかった。
けれども、森下氏は、「独立・開業する勇気や冒険心が全くなく、会社に勤めていれば何とかなると、次の勤め先を探した」という。それは森下氏が父は役所勤め、母は教師という家に生まれ、子供の頃から「寄らば大樹の陰」で安定志向が身についていたからだ。一から会社を起こす、すなわち独立・開業するというベンチャー精神はさらさらなかったという。やがて名古屋の業務用食器洗浄機メーカーから、「専務として来てくれないか」という話が舞い込んできた。従業員が40人近くいる会社だという。
森下氏はこの話に飛びついた。だが40人の会社はハッタリで2階の事務所に4人、1階の工場に2人だけ、たった6人の小さな会社だった。転職して1週間後に30人以上が働く板金の工場に案内してもらった。そこには会社の看板が確かにかかっていたが、別会社の協力工場だという。その社長は、「たった6人の会社では東芝テックのトップセールスマンが来てくれないだろう」と考え、40人の会社だと騙したのだった。
森下氏は自分の甘さを攻めたが、それくらいでへこたれはしなかった。森下氏は東芝テック時代に築き上げた人脈などを活用、直ぐに成果を上げ出した。スキマ製品ではあったがコンベア式大型食器洗浄機は地域の給食センターなどで非常に重宝され、よく売れたからだ。森下氏は会社の2年越しの売掛金6000万円を回収し1年足らずで売上高2倍、利益3倍、社員22人の会社に急成長させた。
それはたった6人の中小企業を経営してきた社長にとって、信じられない躍進だった。社長は森下氏の神がかり的な営業手腕に度肝を抜かれた。営業部隊を中心に専務の森下氏が採用した新入社員達が大きな勢力を形成する中で、社長は自分が会社を追い出されるような気持ちになった。
社長は「こいつは会社を乗っ取るつもりだ!」と、妄想めいたことを言いだした。それが高じてついには森下氏に、「辞めてくれ!会社を引っ掻き回された」と縁切り宣言をするのだ。
森下氏にしてみればひどい濡れ衣だった。森下氏が専務になって10ヵ月目のこと、会社で社長が灰皿を持って森下氏に殴り掛かるような一触即発の事態になった。経理を見ていた奥さんが社長を羽交い絞めにし、事なきを得たが、結局森下氏は部下2人と辞めることにした。当初は同社の東京営業所として設立する話もあったが、「会社の名前も貸さない。資本も出さない」という。森下氏は社長の奥さんと話し合い、食器洗浄機を供給してもらうことにした。
こうして森下氏はクビになった2人の部下と共に、東京・渋谷区に6畳一間のアパートを借りて、そこを拠点に商売を始めたのである。独立開業する気はなかったのに、そうしなければならなくなったのだ。
森下氏にとってこれが初めての起業であり、背水の陣を敷いた。朝4時半ごろから起き出し、築地や旧神田市場(現大田市場)などの卸売市場の食堂に食器洗浄機を売り込みに行った。昼飯、晩飯を食う時間を惜しんで給食センターや企業、団体等の大きな食堂に売り込みに行った。森下氏の図抜けた営業力で食器洗浄機は次第に売れていったが、名古屋との関係が悪く、製品が安定的に供給されなかった。森下氏は大阪や東京の下町の中小零細工場で同じ機械を作ってもらった。ところがなかなか要求するような製品ができなかった。
仕方なしに東京都大田区に倉庫を借りて、そこを工場に改装し、完成品を分解し、見よう見真似で自分たちで業務用食器洗浄機を作った。また、食器洗浄機の修理・補修なども行った。振り返って見れば、これがテンポスバスターズのリサイクル厨房機器販売の原点といえた。
こうして森下氏はバブルに突入する4年ほど前の83年6月、大型連続式食器洗浄機の製造・販売会社の「KyoDo」(現・キョウドウ。東京都大田区)を設立した。ニッチ商品であったが食器器洗浄機はよく売れ、毎年4000~5000万円の経常利益を出した。やがて大田区東蒲田に本社オフィスを構え、技術者や営業マンなどを採用した。
「といってもきつい、汚い、危険の3K職場。人を採用するのは難しかった。それでも毎年右肩上がりで成長。創業10年経つ92年頃には売上高10億円、経常利益1億円強、社員104人、営業所6ヵ所の会社に発展した。ところがバブル崩壊後、業績は年間5~7%落ち込むようになり、食器洗浄機に次ぐ製品開発が急務になった。しかしこれがうまくゆかない。このままではジリ貧に陥ると、私は外国人のゲストハウス、英会話学校、環境調査、回転寿司など7つの新規事業を起こした。中には雨の日にナイロン袋を傘にかぶせる機械「傘袋入れ太郎」(権利を売却)を開発したり、また生ごみを分解する機械を家庭向きに販売する会社を買収して、個人相手に販売した。しかし、軒並み失敗し1億4000万円の損を出した」(森下氏)
新規事業7連敗の最大の原因は森下氏が中途で入社してきた若手社員などから企画を募り、彼らに起業を任せたことにあるようだ。人材の少ない中小企業において新規事業は、トップが責任を持ってやるべき案件だ。それでも新規事業の成功確率は1~2割に過ぎず、8~9割は失敗事業である。
森下氏がそれを若手社員にやらせたのは、人材を育成する目的があったからだと思われる。仮に失敗事業であっても人材を育てるのには、新規事業に挑戦させるのが一番手っ取り早いからである。とはいえ、新規事業に失敗すると仕事を任された社員は、ほとんどが退職していった。