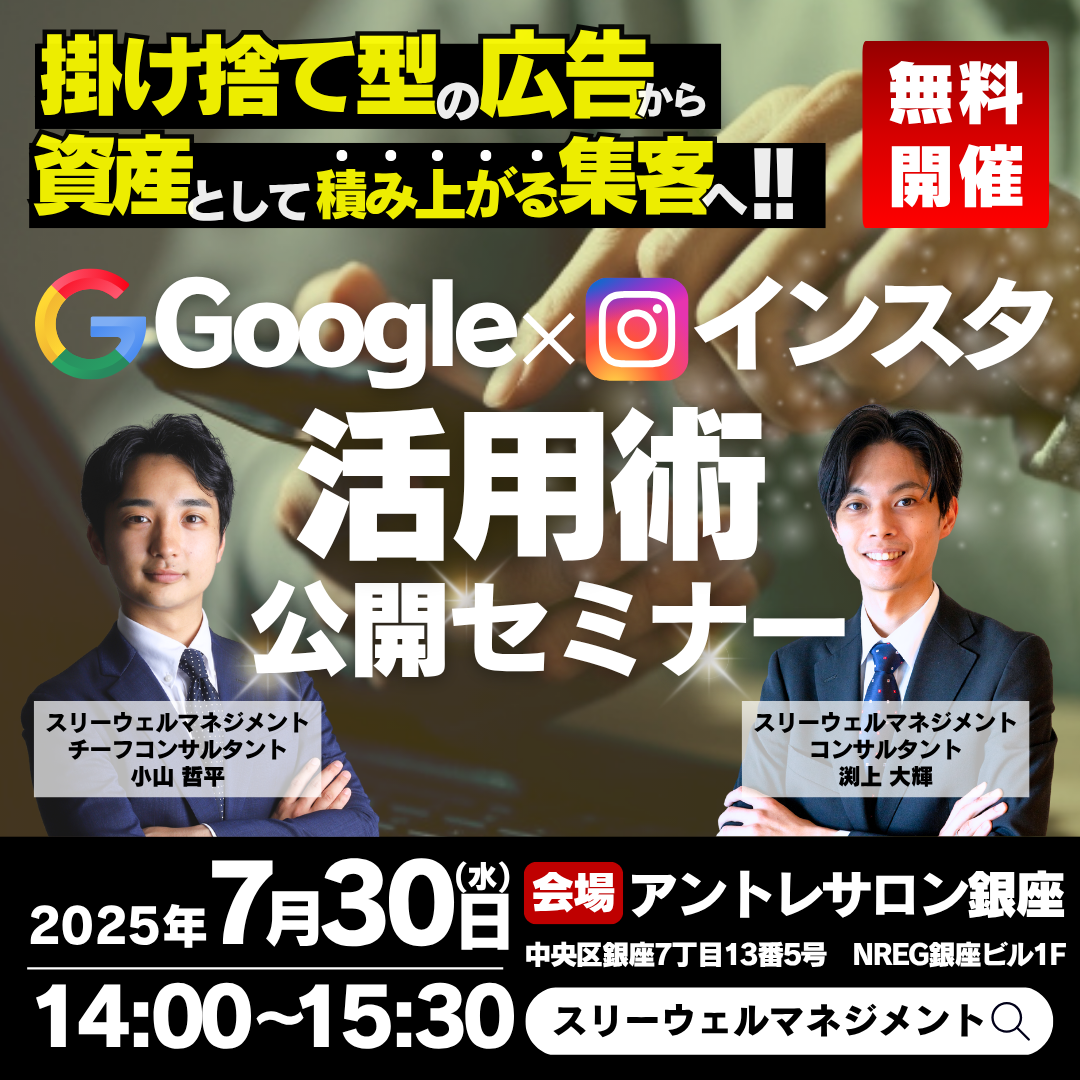メニュー単位での投稿検索に強みをもつグルメアプリ「SARAH」や、食品の企画開発向けデータサービス「FoodDataBank」などを展開する株式会社SARAHが、2024年初にリリースしたのが「ONIGIRI Chain」だ。こちらは食とヘルスケアに特化したブロックチェーンだが、どんな特徴や強みがあり、食の世界をどう変えていくのか。同社代表の酒井勇也氏に聞いた。(後編はこちら)

単なるグルメアプリではないSARAHの独自性
SARAH社は2014年に創業し、翌年に「SARAH」をローンチ。飲食店ではなくメニュー単位で口コミをする点が最大の強みであり、2023年にはトークンとNFTを活用したグルメアプリへ進化した。ユーザーは投稿によってトークンが獲得でき、トークンを集めることで飲食店のNFTが購入できる。
なお、トークン(Token)やNFT(Non-Fungible Token/代替不可能なトークン)はさまざまな意味で解釈されるが、「SARAH」ではトークン=独自ポイント、NFT=常連バッジ/応援証のような形で運用している。

「FoodDataBank」は2019年の12月より提供開始。こちらは「SARAH」に投稿された外食・中食の口コミデータを活用することで、ビッグデータ分析プラットフォームと食品業界特化型のコンサルティング支援を行うサービスだ。
「SARAH」が一品単位の口コミに特化しているからこそ、どんな料理や味付け・食材が求められているのか、トレンドのメニューは何かといった世の中の傾向を簡単に把握でき、食品メーカーは消費者インサイトを反映したコンセプト設計や商品開発が可能となる。

そして「ONIGIRI Chain」は、「SARAH」でも導入している技術を活用したブロックチェーンだが、酒井氏に改めて「SARAH」の世界観から聞いた。
「たとえば、ユーザーさんが投稿すると『UME』という名称のトークンが付与されます。これはポイントのようなもので、1回投稿したら10ポイントみたいなイメージですね。こちらを一定数集めると『NOREN』という各店のバッジのようなものと交換でき、さらに『UME』や投稿の数でランクがわかれています。
いわば『そのお店に何度も通った人=ファン』であることを可視化できるイメージで、店舗側は『NOREN』を獲得したお客様に特典をふるまうといったこともできます」
永続性のあるブロックチェーンならではのイノベーション
そのうえで同社では「FoodDataBank」も展開しているが、将来的にデータベースをブロックチェーンへ活用することを構想する中で生まれたのが「ONIGIRI Chain」だった。

「過去に、ダイエットアプリを展開している企業様から、データベースをカロリー分析や食事のレコメンドに使いたいという声をいただいたり、また、何を食べてきたかによって料金が変動する商品を開発したいという保険会社様がいらっしゃったり、特にヘルスケア領域での可能性を感じていました。
ただしこれまでのサービス間におけるデータ連携は、いわゆるAPI(Application Programming Interface)によるもの。その場合コストもかかりますし、サービスごとに異なる仕様を整えることにも課題があります。加えて、データのプライシングは価格設定が容易ではありません。
一方、ブロックチェーンの世界では規格が統一されているうえ、通貨は日本円以外でも支払いが可能。また、ブロックチェーン技術を使うとデータを永続的に保存できるので、社会に対して普遍的な貢献ができるのではないかという期待もありました」

では具体的に「ONIGIRI Chain」によって何が実現でき、どんなユーザーベネフィットがあるのか。それを握るカギはまさに「永続性」にあるという。
「たとえば、今30歳の方が80歳になったときに大病を患ったとしましょう。その治療に関するひとつのヒントとして、50年間の食生活を振り返ることができるんです。これは従来のサーバー管理型サービスの場合、サービスの終了によって若いころのデータが残っていなかったり、読み込めなかったりするんですね。しかしブロックチェーンであれば、そういった不具合はありません」

さまざまなデータが集まることで、たとえばトマトを毎日食べていた人はそうでない人よりも長生きした、といった研究に貢献できる可能性もあると酒井氏。そんな「ONIGIRI Chain」は複雑にも見えるため、開発には時間を要したと思いきや、約半年でサービスローンチを実現できたという。
「2023年の夏にスタートし、翌2024年の1月31日にリリースできました。このスピード感は、当社が世界的にみても業界トップの企業であるAva Labs社の『Avalancheチェーン』を日本で初めてパートナーシップ締結でき、彼らと一緒に作ることができたからだと思います」

プライバシーを保護するための特別なシステム設計
開発における苦労話を聞くと、ユーザーのプライバシーをどう保護するかという課題があったという。
「ブロックチェーンはある種、データを共同管理するシステムです。私たちが集めているデータは、だれが何を食べたのか、どのような健康状態なのかという情報ですので秘匿性が高く、そのプライバシーは守らなければなりません。
一方で『ONIGIRI Chain』の独自性は世界でも類を見ない事例だったので、データの取り扱いや情報を守る部分に関しては労力と時間をかけて開発しました」
こうしたプライバシーを守るためにシステム設計したのが、だれでもデータを書き込み/閲覧/使用できるパブリックチェーンと、バリデーター(セキュリティ維持の責任をもつ参加者)のみデータの閲覧/使用が可能なプライベートチェーンとで保存先をわけた「ONIGIRI System」だ。その具体的な内容や、今後の展望などは後編で解説しよう。